マイナスをプラスに転換する「雪室」の力
「冬眠という熟成の味を旅する気分で体験してみませんか?」開催レポート

雪や寒さがもたらしてくれるもの
秋田市主催の「文化創造プロジェクト」の一環として、2022年7月にスタートした「PARK – いきるとつくるのにわ (Public, Arts and Research Kitchen)」。
「観察する」「出会う」「育む」「残す」という4つのテーマの元に行われるさまざまな活動があり、「観察する」は、“クリエイターのリサーチと表現”を通じ、当たり前にある秋田の普段の暮らしを新たな視点で見つめ、その価値に気づかせてくれる取り組みです。
参加クリエイターのひとり、わいないきょうこがリサーチしたのは、秋田のフード(風土)。旬の時期に豊富に収穫できる食材の食べ方を再構築し、冬季は「雪室」で眠らせる食材の「熟成(mature)」を観察しました。
2022年12月初旬から、約3ヶ月冬眠した食材たちの目を覚ます「雪室開封の儀」が行われたのは、2023年3月8日。「ごくろうさまでした」と眠っていた命に声をかけ、雪室を開封します。

このプロジェクトの発端は、わいないの幼い頃の記憶。雪が積もる冬季、秋田県美郷町にあった祖母の実家の庭には、雪室があったのだといいます。
「当時の光景を思い出した時に、祖母は、マイナスに感じてしまう雪をプラス転換していたのだと思ったんです。それを自分でも実証したいと思ってプロジェクトを始めました」とわいない。
藁を剥がしていくと、たくさんの食材が現れます。何層もの藁をかけたのは、直射日光を防ぐため。秋田市内は雪が多く積もらないことが想定されていたため、雪室に必要な一定の温度を保つためのアイデアとして取り入れました。


この日は、眠りから目覚めた食材の状態を確認し、2023年3月21日開催予定の調理ワークショップに向けて試作を行いました。一緒につくるのは、〈秋田市文化創造館〉で野菜栽培などを学ぶ「育む」のプロジェクトメンバー。わいないのプロジェクトにも興味をもち、自らサポートしたいと手を挙げたのだといいます。
クリエイターに刺激を受け、市民ひとりひとりが自発的に活動の種をつくり、育てていくことは、本事業が目指す理想のかたち。彼女たちは、雪室に眠らせる加工品の調理からメンバーとして関わり始めました。

料理好き・料理上手なみなさんですが、わいないが世界中で学んできた調理方法は初めて知るものばかり。楽しく、学び多いものとして参加していると話します。雪室による熟成もそうで、採れ立てで食べるよりも旨味や甘味が増した食材に感激しているようでした。
「いつ災害や戦禍に見舞われるかわからない今、1日1日を大事に生きる、ある食材を無駄にしないで活用する、少しでもものを捨てない--。そういう気持ちで地球と向き合うようになってもらえたら素敵だなと思っています。雪室プロジェクトに参加する彼女たちがそうしてくれたら、次の世代や、まちの隣人に波及していくと思うんです。地球のリズムに反せずにものを食べるということは、ただもったいないからということではなくて、大事にするということ。それがイコール隣人を大切にすることだと思うから」とわいない。
雪室プロジェクトは、地の食材と向き合うひとつのきっかけ。根底には、地球に対して感じている危機感があります。
「すべての物事に対して、誰が悪者かを決めたいという風潮になってきている気がします。“怒り(anger)”のようなネガティブな感情から生まれるものではない、“創ること(creation)”ができる暮らしは、安住できる場所があってこそ。今日のように食べ、おいしいと思える人と一緒にいられる環境は、当たり前ではないことを、私たちはわからなくてはいけないんですね」
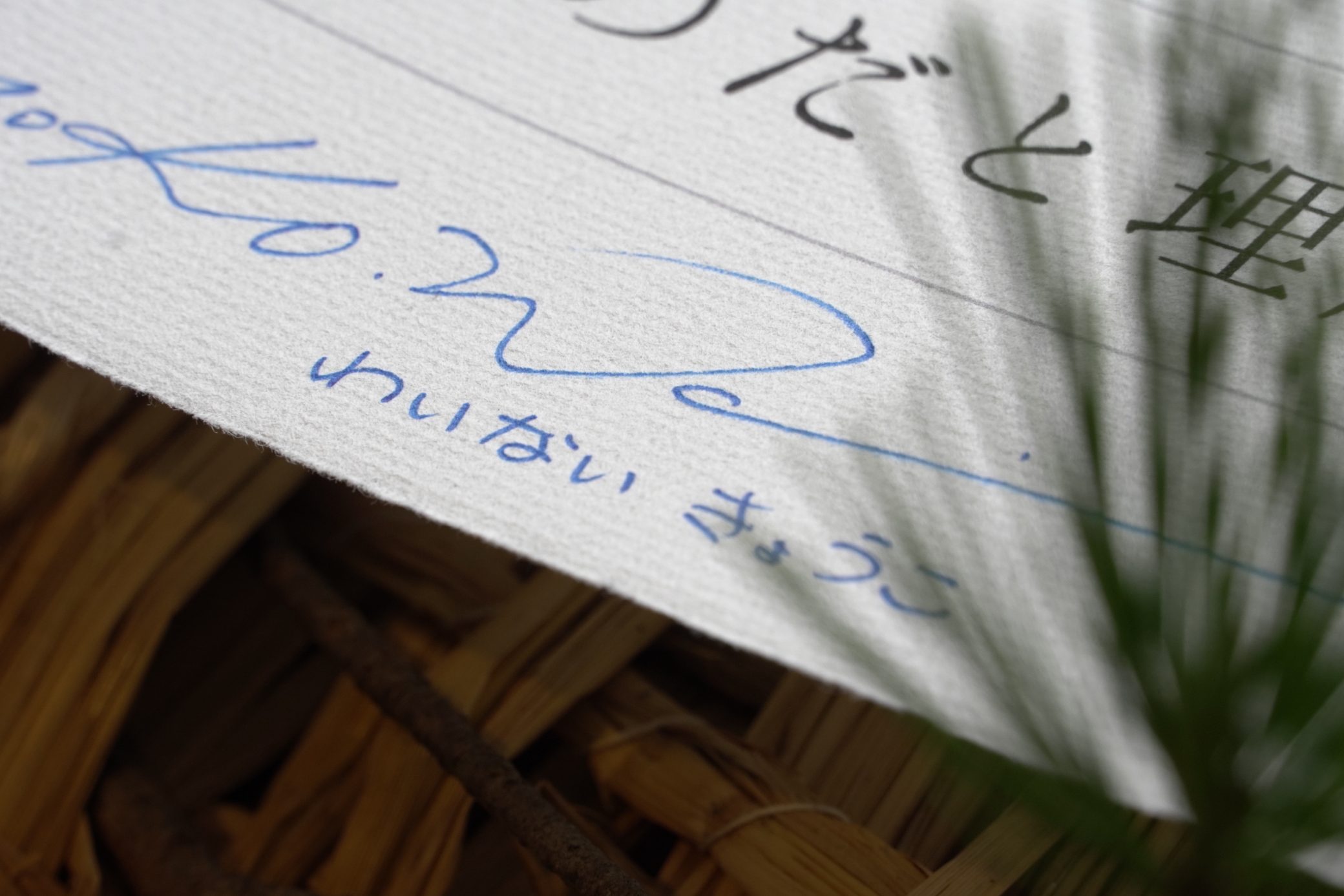
秋田に暮らしていると、ネガティブに捉えてしまう冬や雪。けれどもそれらも、怒りにするのではなく、見方を変えれば素晴らしいものであること、それを教えてくれるひとつが、雪室です。
「これからいろんなことが起きると思いますが、その状況に適応して生きていく価値観の転換をすることが、クリエイターが本当にやらなくてはいけない仕事なのではないかと思っています。すべて新しく開発するのではなく、あるものをひとつひとつ見直していって、見方を変えていくことに答えがある。市民と一緒に、頭を使って考える、それが大事なことなのではないかと思っています」
今の暮らしが豊かであることを自覚する
〈秋田市文化創造館〉が開館2周年を迎えた2023年3月21日、芝生広場でトークイベント&料理ワークショップ『冬眠という熟成の味を旅する気分で体験してみませんか?』が開催されました。

2月上旬までの約1か月、ヨーロッパに滞在したわいない。スペイン、南仏、イギリス、イタリア、ドイツを渡り、特にベルリンでは、すぐそばで戦争が起こっている気配も感じたことをトーク冒頭に話します。
「人々の食生活は、まだなんとか守られている感じはありました。けれども、物価も高くなって、これからヨーロッパでも食生活がどんどん変わっていくと思われます。特にイギリスはEUを脱退したので、かつてのように、豊富に新鮮なヨーロッパの食物が手に入る状況からは少し変わっていました。
いろんなところの食物が、いろんなところを回遊して口に入るということ。そのことに私たちは慣れていますが、それは本来の人間の営みではないんですよね。
新鮮な地のものを口にできる秋田という土地で、わざわざ遠くから運ばれてきたものを食べるというのはちょっと違うのではないか――。そういうことを考えてほしいと思っています。
一度に採れる野菜がたくさんあることが、どれだけ貴重で豊かであるか。これから私たちは何を食べて、何を加工して、何にありがとうと言える暮らしにしていくのか。それらを考えることはとても大事なことです」
料理ワークショップでは、3月8日の試作を元に考えられたスペシャルメニューが並びました。 スタートは「ブルスケッタ」。パンに塗るのは、雪室で熟成した酒粕です。美郷町の〈栗林酒造店(春霞)〉の酒粕が、冬眠したことでクリームチーズのような味わいに。これに焼いたニンニク・ホワイト六片とブラックペッパーを混ぜ、パンチェッタとアンチョビ、ピクルスをのせていただきます。

パンチェッタは一般的には豚バラを塩漬けにしたものですが、今回はスペアリブを塩漬けにし、雪室で眠らせました。そのまま食べると生ハム、火を通すとベーコンのようです。骨はスープに使います。
アンチョビは、一般的にはカタクチイワシの塩漬けですが、秋田県の県魚でもある名物ハタハタの塩漬けに挑戦。雪室から目を覚ますと、身そのものをおいしくいただけることはもちろん、ドリップも魚醤の「しょっつる」のような旨味を含んだ調味料になりました。
いずれも〈秋田市民市場〉で仕入れた、秋田で獲れた・育った食材です。

熟成という旅をして、旨味を増したパンチェッタとハタハタが、この日のメニューの主役。サラダにもメインのパエリアにも、スープにも入ります。
そして、サラダに入るキャベツと白菜、ニンジンとジャガイモ。スープに入るセリと白菜、沼山大根。パエリアに入る玉ねぎ、ニンニク、ムカゴ、キクイモ、銀杏、そしてお米も、みな雪室で熟成されたもの。
それらもみな、秋田で収穫されたごくごく身近なものです。
冬眠という名の熟成の時間と、わいないが世界中で出会ったシンプルな調理のアイデアを加えることで、目の前にあるものが魅力的になり、自分たちでもその魅力を再現できる。参加者がそのことに気がついていることは、表情から伝わってきました。

広い空の下、薪で火を起こし、大きな鍋で煮込む温かいスープ。これはまた、「怒りではないクリエイション」を生むためにわいないが大切だと考える、「安住/安心/Homeを感じられるもの」をメニューに表現したものです。
インスピレーションを受けたのは、ドキュメンタリー『マリウポリ 7日間の記録』。
ロシア軍が占領下に置く、ウクライナ東部の港湾都市・マリウポリに生きる人々の日常を映し出した映像には、瓦礫の中で火を焚き、スープをつくるシーンが登場します。

「どうしてもそのスープが飲みたかった、と言って、つくっているんです。私たちには臓器に染み渡っていくおいしさという感覚があって、そのことに感謝できるスープは、命を繋いでいく食べ物だと思います。
戦争なんて起きてほしくないし、大きな災害も起こってほしくないけれど、調子が悪いなと思ったときに口にしたいものって、温かいスープ、温かい味噌汁なのではないか。そこに味噌やピクルスのように発酵・熟成したものがひとつでも入っていると、それは“腑に落ちる”。体への吸収を助けてくれる、安心の味にしてくれているんだなということを、ここ最近感じています」
——————————-
スープ・味噌汁という命を繋ぐもの
マニウポリの瓦礫の中でのスープ。
それがインスピレーション。
ロンドンの正教会で、ルーマニアの友人宅で、
横浜の父方の祖母が作った
それなんだと思えます。
ハーブと根のものとピクルス
(熟成、発酵した味のもの)
それが入ると腑に落ちる味に。
日本だと味噌であり漬物であり
それがその味に。
祖母が作ってくれた
浸かりすぎた菜葉の漬物をごま油で炒めて
大根など根菜をさっさと入れてスープに。
そういう味は
なんかロシアにも繋がる味に感じていたり。
今回の雪室で生き延びた野菜と
出来上がったアンチョビとパンチェッタ
それぞれのシンプルなスープは
どこの国のものでもない祖母の味。
ロシアと日本を跨いだ味。
どんなところにいても
どんなことが起きていても
お腹はいつも満たされていたい。
安心という時を得るために
満たされた腹にはスープ、味噌汁。
世界中のどこででも食されていることは
間違いない。
わいないきょうこ
——————————-

料理ワークショップを締めくくるデザートは、雪室で熟成されたリンゴそのものの味を体感できることはもちろん、「どさっと食べる」という体験をしてもらいたかったとつくった「焼きリンゴ」。すぐそばに恵みが潤沢にあるからこその贅沢です。

この日、会場には、わいないが秋田で出会った、自分で活動の種をまき、育ててきた友人たちがたくさん訪れていました。
食材のみならず、秋田で生きる人たちのありのままの価値を浮かび上らせ、自然と伝えてくれるのもまた、わいないの力・魅力です。



秋田という場所で活躍するたくさんの人たち。目の前のものをプラスに変えられるのは、自分自身の思考です。
「足元でちゃんと育っているものを口にすることは、ワンパターンでつまらないものでは決してないのです。ちょっと見方を変えれば、おいしいものと楽しい暮らしがあって、こんなに贅沢なところはないと、秋田という土地のことを思うようになるはず」とわいない。
ローカルなフード(風土)を見つめ直す取り組みからから生まれた雪室プロジェクト。
ひとつの場所で、時間が食物に影響していく過程を観察していく「定点観測」は、今年限りではありません。観察には時間が必要。世界中にある熟成方法や調理方法を学び、そばにあるものを尊び、共に生きることを考えていく――。わいないのプロジェクトは、また来年も、つづきます。

Profile

わいないきょうこ(デザイナー、やぶ前)
横浜市出身。桑沢デザイン研究所写真研究課卒。日本でバッグデザイナーとしてそのキャリアをスタート、活動拠点をロンドンに移した後は、内外問わず様々な企業やデザイナーとのコラボレーションを通じ、バッグを主軸にファッショ ン小物やインテリア・オブジェなどを制作。また舞台、映画などのコスチュームデザインも担当。 現在はブータン王立タラヤナ財団クリエイティブアドバイザーなど続けながら、ロンドンのスタジオを母方のルーツ秋田美郷町に移し、町の人々と伝統と知恵を新しく捕まえる形で世界にその暮らしぶりを伝えるための町の学び舎’やぶ前’を始めた。
撮影| 白田佐輔
取材・編集|佐藤春菜
▶︎「PARK – いきるとつくるのにわ」についてはこちら
▶︎「冬眠という熟成の味を旅する気分で体験してみませんか?」イベント開催概要



