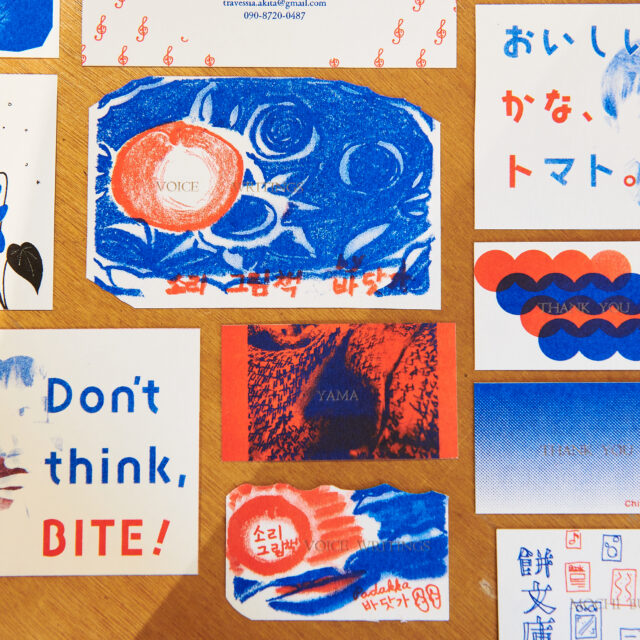デモンストレーション+トーク
「大地とつながるひと皿」レポート
日時|2025年2月20日(木)18:30-20:15
会場|秋田市文化創造館 1階 コミュニティスペース

秋田に暮らす人々やクリエイター、専門家が交わり多様な活動を展開するプロジェクト「PARK – いきるとつくるのにわ」。「観察する」「出会う」「育む」「残す」の4つのプログラムを通して、秋田の文化的土壌をたがやしていくことを試みます。
この度は、「育む(手を動かしつくることを実践する場)」番外編として、秋田の天然素材を活かした土づくりに挑む農家・沢田石武瑠さんとフレンチシェフ・渡邊健一さんによるトーク、そして沢田石さんの九条ネギを題材に、素材の魅力を活かす料理のデモンストレーションを行いました。
秋田の文化の発信に取り組まれているフリーパーソナリティ、地域文化コーディネーターの椎名恵さんによるイベントレポートを公開します。
一人でフレンチを味わう
私が初めてその経験をしたのは、取材で訪れた「レメデニカホ」だった。
誰とも会話せず、料理と向き合い、じっくりと目で楽しみ、ゆっくりと口に運ぶ。
そこには、これまでにない新たな体験があった。
一皿の料理から、シェフのおもてなしの心、秋田の食材への誇り、農家や生産者の想い―
それらが目の前の一皿に込められ、まるで物語のよう。料理に対して「愛おしさ」を感じた。 そこでふと思ったことがある。もしかしたら私は今まで「なんとなく食べる」をしてきたかも?なんなら忙しい時は楽しむことを忘れて「済ませる」もしているかもしれない。
「食べるってなんだろう、満たされるってどういうことなんだろう?」 その答えを、今回のデモンストレーション+トークでみつけられた気がする。

農地と厨房を飛び出して

20代という若さで、秋田で九条ネギの栽培に挑む、農家・SENTEの沢田石武瑠さん。
九条ネギは京都の伝統野菜として知られるが、「冬の京都が寒いなら、秋田でもフレッシュな九条ネギを育てられるのでは?」
そんな発想から、秋田の地で九条ネギ栽培に取り組む新たな挑戦が始まった。
明治から続く実家の農家を継ぎ、秋田の天然素材を活かした豊かな土づくりに尽力。さらに、つながりのない県外の農家のトップランナーへ直接電話をかけ研修を申し出て、車中泊をしながら修行を重ねるなど、圧倒的な行動力と熱意がとにかくすごいと思った。
さらに、気候変動を逆手にとり、「秋田で年中新鮮な野菜を作ることはできないか?」と可能性を探っている。柔軟な発想と挑戦する姿勢は、まるで一本筋の通った九条ネギのよう!


一方、フレンチの世界で長年腕を磨いてきた、Remede Nikahoのオーナーシェフ、渡邊健一さん。志したきっかけは「料理学校でフレンチを教えてくれた先生が、一番楽しそうに料理をしていたから」。
昔から心が惹かれる方向へワクワクしながら進んできたのだろう。そう想像すると、なんだか微笑ましかった。
「フランス料理は、長い歴史の中で積み上げられた技法をベースに、異文化の食材や調理法を柔軟に取り入れながら進化してきたもの。」
その言葉の通り、秋田の食材とフレンチを融合させ、新たな料理を生み出している。
「厨房を飛び出してこうして話をすることで、食に興味がある人達だけではなく、さまざまな人に食の楽しさ、大切さを伝えたい」そんな強い想いが渡邊さんの言葉からどばどば溢れ出てくる。
お二人の挑戦と無限に広がる思いに、私は引き込まれていった。

後半は、PARKならではの企画「体験する」ワークショップが展開された。
まず、一人ひとりにオリジナルレシピを考えるワークシートが配られる。 はじめに、こんな質問が投げかけられた。
「みなさん、料理は好きですか?それとも苦手ですか?」
私は少し恥ずかしさを感じながら、そっと後者に手を挙げました。。

「料理をするとき作るものから決めますか?それとも冷蔵庫の食材をみて考えますか?」
私は前者で、今日はマーボー豆腐をつくるぞ!とゴールから決めるタイプだけど、今回のワークは目から鱗がおちるハッとさせられる体験になった。
ここから、目の前の食材を見てどのように活かすかを考えるワークが始まった。
まずは(味・香り・食感・色彩・その他)など、素材を観察することから。九条ネギを、白い部分と青い部分に分けて、生・炒めで味わう。まず、味見してみてまったくちがう性格だということが分かっておどろいた。


(以下は私が書いた素材の観察メモ)
生 → 脳内に響くシャキシャキとした歯ざわり、繊維感、透明感、辛みがなく甘い
炒め → 色が濃くてbeautiful、バターのようなコク、とにかくあまーい、口当たりなめらか
次に、素材の特徴をどう活かすか。
渡邊さんは九条ネギの美味しさをダイレクトに味わってほしいという理由で「ポタージュ」をつくることに。
フライパンより熱い参加者の視線を浴びながら、キッチンでは渡邊さんの実演が始まった

出来上がったポタージュは、それはそれは香りがよく、九条ネギの旨みと甘みが広がる深い味わい。同席した参加者の方と、この香りのアロマが欲しいと話題になりました。是非ずっと香っていたい。いつか商品にしてください「九条ネギアロマ」笑
ワークシートに書き込んでいくうちに、「ただ食べる」のではなく、素材の個性を知り、活かすことの楽しさを実感した。
「料理はレシピ通りに作るもの」と思い込んでいた私にとって、今回の体験は「自分の好みで料理を作る楽しさ」に気づくきっかけとなったと思う。
そして「食べること」は、心と体が満たされること。農家さんと料理人が対話しながら食材と向き合うように、私も日々の食事をもっと丁寧に楽しもうと思った。


今回、沢田石さんと渡邊さんの対話に、深く心を揺さぶられた。
これまで私はパーソナリティとして、そして地域文化をコーディネートする活動を通して多くの方に出会う中で、その人の挑戦や情熱、信念に触れるたびに、自分自身の視点が広がるのを感じてきた。
九条ネギの変化を楽しんだように、地域の文化もまた新たな視点で見つめ直すことで、その価値がより輝くのではないか。そして、多くの人にお二人の意識を伝え、共感を広げていくことで、地域全体が豊かになっていくのではないか。
私にできることは何か? それは、人に伝えるコトと人に伝わるコトのちがいを意識して「伝え続けること」だと思った。沢田石さんや渡邊さんがそれぞれの立場で熱意を持って行動しているように、私もまた、自分なりの表現で秋田の魅力を伝えていこう。

Profile

椎名 恵(しいな・めぐみ)
18 歳の時にエフエム秋田の番組オーディションでラジオパーソナリティとしてデビュー。以降フリーランスで、ラジオやテレビの情報番組、 ナレーション、イベント MC 、婚礼式典司会、講演会、商品プロデュースなどを行う。 秋田の文化、歴史や風土体験が好きで、井川町の田んぼで酒米から育て五城目町の福禄寿酒造で仕込む日本酒造り 「桜名月」の活動や、地域文化コーディネーターとして、 秋田大学地域学基礎講座「秋田の提灯文化とブランディング(2023)」、「秋田の版画文化とブランド戦略(2024)」。今年は、版画家勝平得之生誕 120 年を記念して地元に根付いたお菓子屋と学生と一緒に「版画家勝平得之とお菓子文化プロジェクト(2025)」がスタート。生まれた町内の竿燈まつりに参加してきて秋田竿燈まつりへの思いが深く、現在は竿燈まつりの提灯職人と共に提灯文化を広げるための発信に力を注いでいる。
▶︎デモンストレーション+トーク「大地とつながるひと皿」については こちら
▶︎「PARK – いきるとつくるのにわ」についてはこちら
記録写真:伊藤靖史(Creative Peg Works)