「未来の生活を考えるスクール」第13回開催レポート 後編
アニマルズ、ヒューマンズ、アスレチック
日時:2023年8月19日(日)14:00〜17:00
ゲスト:山口未花子さん、山川冬樹さん、石倉敏明さん
主催:秋田市文化創造館

新しい知識・視点に出会い、今よりちょっと先の生活を考えるレクチャーシリーズ、「未来の生活を考えるスクール」。
第13回では、狩猟の研究を行う人類学者の山口未花子さん、美術家・ホーメイ歌手として活動する山川冬樹さん、文化人類学と芸術表現の可能性を研究する石倉敏明さんをゲストに迎え、トーク・ワークショップを行いました。
秋田市文化創造館で新たに始まったプロジェクト『〜になるためのトライアル』の一例となるユニークな活動を行うゲストを招き、「人間以外の種と交わりながら生きる術」そして「身体を使って表現をする術」について考えます。人間のために整えられた社会の中で薄まってしまった人間の能力、あり得たかもしれない人間のかたちを見つめ、これからあなたに訪れる「~になる」を自由に発想してみましょう。
世界と周波数を合わせる
司会 山口さんの紹介されたユーコンの準州の事例は、日本での暮らしにどう結びつけて考えられると思いますか。
山口 実際、私もカナダにいるときと日本にいるときで、同じ私という人間でも、在り方が違ってきます。例えばカナダに行くと肉ばかり食べてすごく動くので筋肉が付くんですよ。日本に帰ってくると野菜や魚もよく食べるので、筋肉が落ちていって違う体つきになります。
またカナダにいるときは、いろんな感覚を使っている感じがします。6カ月間カナダの森の中にいて、東京に帰った翌日に渋谷のスクランブル交差点を歩こうとしたら、人にぶつかって歩けなかったです。あと電車も1駅ごとに降りて休んで、また次の駅に行くという感じで本当にすごくしんどかったです。入ってくるたくさんの情報を処理し切れなくて。3、4日たつと普通に渋谷も電車も平気になったのですが、そのときは体のいろんな感覚が閉じて、都市で暮らせる体になっていったのだと思います。生きる場所が変わるだけで、人間の体ってすぐ変わると思うんです。

カナダで狩猟詩集をずっと続けているおじいちゃんも、インディアンでなくても自然の中や空が開けた空間にいって動物のことを考える、思考を外に開けることをしていると、だんだんいろんな物が聞こえるようになってくると言っていました。
なので、日本にいるからできないとか、先住民の文化で生まれ育って鍛えられているからできるということではなくて、人間に本来備わっている感覚や自然とコミュニケーションできる力があることを知らない、きっかけがないだけじゃないかと思うようになりました。それこそアートや人類学が今の社会でもしやれることがあるとしたら、そのきっかけになることかなと思います。カナダやモンゴルやシシ踊りのような動物と密接でコミュニケーションがとれる関係は日本とも連続していると気付いてもらえるといいですし、それは日本でも実現可能だと思っています。
山川 僕はずっと東京首都圏に住んできたんですが秋田に住み始めて、自分の感覚が変わったと感じています。自然に口から歌が漏れるようになったり、美術館で作品を見るときに自分の目が変わったと気付いたり。つまり自分の身体に秋田の環境や風土が与えている影響は確実にあるなと。そしてこれを突き詰めて考えていくと、秋田の文化に行きつくと思うんです。
例えば秋田って石井漠や土方巽という天才的な舞踊家が出ていますよね。あと無形民俗文化財も日本で一番多い。環境が踊りや身体を動かす人たちに影響を与えてきた。そしてモダンダンスや前衛的な舞踏の芸術家たちの身体にも影響を与えてきたし、秋田に住んでいる皆さんの身体にも影響を与えている。東京と秋田を往復しているとそのコントラストが分かるんです。自分が環境から受けていることをモニタリングできる、みたいな。
お話を聞いて思い出したのが、2015年に『渋谷ウォーターウィッチング』という作品をやったことがあるんです。渋谷って昔はすごく水系の豊かな場所で、今は暗渠や下水になっていますが、その地下水脈を探るフィールドワークです。

渋谷のマンホールを回りながら、その音を聞いて録音する。聞くときはマンホールの小さな穴に自分の耳の穴を重ね合わせて、下水道のチューブと自分の体のチューブをがちゃっとつなげるイメージです。
僕がトゥバで一番学んだことは、世界の聴き方なんですよ。ホーメイのような特異な歌唱法が生まれたのもトゥバの環境が育ててきた聴覚ありきなんです。トゥバの人たち、めちゃくちゃ耳がいいんですよ。その耳が自分の声に向かったときに、あの特異な響きを発見し、それが洗練されて歌唱法になったのだと思います。僕はそれを現地で学んで東京に帰ってきて、この身体感覚をなにかにできないかなと思ってやった試みです。
結構勇気いるんですよ。車が来ないかを見計らって、渋谷の車道のマンホールに耳を当てにいく。お巡りさんに職質されたり、通行人にびっくりされたりもします。大人って街では直立してないと駄目という暗黙のルールに縛られているじゃないですか。でも子どもはすぐ寝転がったり、何でも口に入れたり、汚いからやめなさい、みたいな野蛮なことを平気でやりまくるじゃないですか。でも大人になるにつれてそういう野蛮なことをだんだんやらなくなって、僕も普段はやらないですよ。でもそれをアートということにかこつけてやれちゃうんですよね。
みんな最近、ノイズキャンセリング機能の付いている耳栓みたいなイヤホンをしてますよね。職質してきた宇田川交番のお巡りさんも宇田川という川が自分の交番の下に流れていることも知らなくて。そうやって近代化の過程でいろんな物が分断されて見えなくなっている。でもそこでチャンネルを替えて深層の風景を耳で見つけてみる。耳からランドスケープや地図が自分の中で出来上がってきて、一つの風景の見方を手に入れる。
石倉 山川さんは、都市の周波数に耳を澄ませる、すごく繊細にチューニングをしているんだと思います。それは山口さんが言っていた動物に周波数を合わせることと通じているはずだと思います。アートと人類学の中間地帯で仕事をしていて思うのは、優れたアーティストと優れた人類学者はとてもよく似ていて、チューニングの上手な人が多いんです。例えば山口さんは森に入ったら動物がどこにいるか、本当に人間の知覚じゃないところに周波数を合わせていって撃つんです。それは人間の世界の外なんですよ。都市に住んでいる僕たちにしてみたら、違う周波数が流れている空間にどうやって周波数を合わせるのか分からないけれど、優れたフィールドワーカーはそこに自分も入っていく。そして、都市に戻ってきたときに何ができるのか。

山口さんの研究会は舞踏家や詩人やアーティストがいて、人類学者が論文を発表するというのと全然違うんです。マルチチャンネルで、いろんな周波数を合わせあう。
また山川さんがやっている周波数の合わせ方。渋谷なんてかつては寝てる人がいっぱいいましたけども、今はベンチにとげが付いていたり遮蔽があったりして横になることすらできないわけですよね。そういう中で人間は立って歩くか、一時的に腰を休めるぐらいしか身体運動ができなくなってしまった。そこでも人間は周波数を合わすことができるんだということ、これはアーティストがやるポイントだと思います。だから、都会であれ、森の中であれ、人間が自然という環境に接してない場所なんて一ヶ所もない。そこで動物になるということを通じて、ハンターは動物に周波数を合わせていくし、アーティストは自分が住む世界に周波数を合わせていくのかなと思います。
具体との往復運動
山口 人類学者は学者なので、いろんなフィールドワークで得た経験、学んだ知恵も論文に書いて「成果です」と出さなきゃいけない。それによって研究として成り立つ部分もありますが、そぎ落とされてしまう物があると思っています。それは都市の生活に似ていて、情報を省略したり抽象化したりすることによって、効率がよくなり安全になり蓄積できるようになるんですけど、手探りで何かをやりながら身に付けていくことがすごく少なくなってしまうと思います。その揺り戻し、バランスを取るものがアートや、人類学におけるフィールドとの往復運動なのかなと感じます。具体的な物とのやりとりを通して新しいものを見つけていくことが大事なのだと思いました。

山川 具体的ってすごく大事なことだと思うんです。感覚的というとふわっとしたものに捉えられてしまうことも多いんですが、体の五感、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚がそれぞれ捉えている知覚はとても具体的なもので、それをどう自分で受け取って解釈するのかにもまた隔たりがあると思います。
トゥバだと家畜のお乳を出やすくするために動物に歌いかけたりするんです。これは機能的で理にかなった牧畜の技術ですが、日本で話すとロマンチックな話に受け取られる。あと例えばホーメイを習うときに、遠くの山並みを見て、その稜線を倍音でなぞるように教わったりするんです。こういう話をすると、ロマンチックに受け取られるんだけど、これもすごく理にかなってて、身体の状態と風景のイメージをセットで体に記憶させることで、風景をトリガーに、いつでもホーメイを歌う時の身体の状態を呼び出せるようになる。そのための訓練なんですね。本当はそこに具体性や理にかなった思想や知性があるんだけど、それを伝えるのが難しいといつも思うんです。
山口 猟をする人たちは、ポータブルなちっちゃい動物の像をお守りにして持っている人が多いという話があって、それは狩猟をするときに動物の形をちゃんとインプットすることが技術として大事だからだと思うんです。森の中に隠れている動物を見つけ出すのって難しいし、シルエットだけで見つけられると取れる確率がすごく上がります。具体的に形を把握していたり、上手に作れる人っていい猟師でもあると思うんです。だから、もともとのアートみたいなものって、もしかしてそこにあったのかなと思います。
あとトゥバの人たちのように、森の中や広大な草原では視覚より聴覚が大事になってくるから、音に敏感であり、いい耳を持つことができる。そういう環境や身体が具体的に持っている感覚によって表現やアートが変わってくることもあるのかなと思います。
山川 感覚的なことって、言葉を尽くして説明しても伝わらず、やはり感覚でしか理解できないのですかね。味が分かるかどうか、みたいな。レシピは言葉で伝えることができるけど、具体的な味みたいな感覚は、感覚でしか伝わらない。
秋田に来て、食べ物がめちゃくちゃおいしいなと思ったんです。どの店に入っても外れがなくて明らかにレベルが高いんですよ。それは秋田の人たちの舌が肥えている、つまり味覚の解像度が高いから、自然においしいお店が多くなっていて。料理も芸術と言うことができますが、観客の感覚が文化を育てているというのは確実にあると思います。
環境を受け入れて野生になる
山川 僕は一時期、ペットショップで鳥と対話する遊びをよくやっていたんです。ホーメイで培った技術を駆使しながら、向こうが鳴いたら、それを模倣して同じ音を返すんです。本当にキャッチボールする感じで。そうすると、「え?おまえ、何?しゃべれんの?」みたいな感じの瞬間があってセッションになるんです。鳥って1羽で飼われていると仲間が欲しいから、人間にコミュニケーションを求めて人間の言葉をまねし始めるんですね。
あるとき鳥との対話がとてもいい感じになって、ほとんど音楽になったんですね、本当にミュージシャンとセッションやる感覚と同じで。その瞬間にあった感覚を僕は演奏に翻訳している気がするんです。
『歌舞伎超祭』というフェスティバルのときは、歌舞伎町タワーを造っている鉄鋼の職人さんが、ギュイーンと鉄を切っている音が聴こえてきました。すかさずその職人さんが出すノイズと全く同じノイズで、ギュイーンと返したらまたギュイーンって返って来て、どんどんセッションになっていって、お客さんも大喜びでした。模倣が、会話になって、セッションになって、音楽になって、アートになっていく瞬間をそのときは観客に見てもらえたと思っています。
「ノイズ」という概念の創始者とされるルイージ・ルッソロという人も、当時は都市化が進んでいろんな騒音が環境の中に出てきたときに、それを楽器のような騒音装置で模倣しました。これってトゥバの人たちが自然を描写して音楽を作ったのと根本的な発想は同じだと思うんです。実は時代ごとのアーティストがその感覚とともに何を考えていたのかは、いわゆる美術史で記述されているいろんな文脈と別に見ていくといろんな発見があって、そこには野生の感覚みたいなものを見つけることができる気がします。

石倉 秋田もですけど春先の草の力ってすごくて、アスファルトの隙間からものすごい勢いで生えているんですよ。カブトムシや小さな昆虫たちも原生林みたいな場所に限らず、人間がかなり干渉している所でもしぶとく生きているじゃないですか。そういう意味では、人間がつくり出した環境も、原生的にある自然も同じように感受している。そこで野生を見いだせるかどうか、生命力を表現できるかどうかってアートにとっても大事だし、生きるということ自体にとって、すごく大きな問いになっていると思うんです。このプロジェクトの中でも、人間以外のものになるとか他の種と関わるってことが問われると思いますが、そこで大事なポイントは自然に帰ることだけではなくて、人間が作り出した物も一つの環境として受け入れて、さらに野生になっていけるのかどうかなのだと思います。
会場からの質問

Q.私たちと動物の関わり方として、狩猟や家畜、崇める対象としての関わりがありますが、現代のペットという存在についてどう思われますか。
山口 動物が好きってなったら、素直に飼いたいと思うじゃないですか。私も子どもの頃、京都の田舎の方で暮らしていて、ヒヨコやウズラ、ウサギ、イヌ、ヤギまで飼っていました。でも中学から埼玉の自由の森学園の寮に入ることになったので、私がお年玉で買い集めた動物なのにそのまま親に預けて引っ越してしまったんです。飼っていたときは楽しかったし、世話するのも苦じゃなかったんですけど、私が寮生活をしている間に動物が次々と死んでいってすごくショックを受けました。人間が動物を飼うことって動物にすごく悪いことなんじゃないかと思って、そこから動物を飼うことが怖くなってしまいました。
一方で自由の森学園は、森の中の学校だったので外に行けばいろんな動物が住んでいて、野外で野生動物を観察することを生物の先生と一緒に始めました。そこで動物は外にいるほうが生き生きしていると感じて、動物本来のいい状態でいられる所にこちら側が出かけていって関わるようになりました。だから私は今、狩猟をして動物を獲るほうが、動物にとっても自分にとっても納得できる関係だと思っています。とはいっても、イヌやネコみたいに人間と暮らすことに慣れている動物もいますね。
石倉 僕がインドのダージリンでフィールドワークしたときに、生き神様と半年ぐらい一緒に暮らしていたんです。インドでは普通、動物を飼うといつか食べるんだけど、その家だけは一緒に生きるために動物を育てているんです。所有しているというより、ただ生きることを許容する空間があって。ペットというのは愛玩動物で人間が保護して可愛がる対象なんだけど、一緒に生きる動物というのを最近の哲学や人類学の概念だとコンパニオンスピーシーズ/コンパニオンアニマルと言います。つまり人間は目的に応じて、家畜として食べたり、可愛がったり、所有したり、あるいは一緒に生きるということもあり、いろんな可能性があり得るんだと思います。

Q.私は狩猟免許を持っていてたまに猟にも行くのですが、殺めることにはまだ抵抗があります。実猟講習会で先輩の漁師がミスをしてキツネを撃てなかったんです。それを見て、すごくきれいなキツネが殺されなくてよかったと安堵してしまったんですよね。
自分が美しいとか好きだなと思う動物を狩って食べることをどういうふうに捉えているのか、お聞きしたいです。
山口 殺すと考えると、その動物のいろんな物を奪ってしまうという気もするんですけど、まず一つ、殺すと考えないというのがあると思います。私がカナダの先住民の人たちと一緒に暮らしている中では、肉はもらうけどまた再生するし、動物の体が人間の中に入ってきて、人間もまた土に還っていって、そこから草が生えて、という全部がつながっていると考えています。
私自身カナダで調査していて、動物が来てくれて贈り物として差し出されているのに受け取らないのは失礼なので、ちゃんと受け取って喜んで使わせてもらうことが動物に対しての礼儀と考えています。逆にキャッチ・アンド・リリースはせっかく魚が来てくれたのに、プレゼントをいらないと言って戻すみたいでむしろ良くない。そうすると、魚がもう二度と来てくれなくなるという考え方です。

でも実際にやってみないと自分がどんな感情になるかは分からないです。いろんな学生を連れて狩猟をして、狩猟免許を持っている学生には止め刺しをさせるんですけど、殺せる子と殺せないが半々ぐらいです。
動物のことを想像して、どこに罠を掛けたらかかるだろうかとか、山を回ってやっと見つけて撃てたという喜び、動物に認められた喜び。あと、この部位はこういうふうに食べようとか、あの人にあげる約束していたからやっとあげられるとか、そういう取れた後の楽しみ喜びがたくさんあればあるほど、殺すことに抵抗はなくなる気もします。

Q.先ほどインコとセッションをしたお話がありました。僕が小学校のとき飼っていた金魚は父親が通った時だけ餌を求めて水面でぱくぱくすると祖母が言っていて、当時は金魚が懐くことはないだろうと思っていました。
今日お話を聞いて、祖母の方が魚とコミュニケーションがとれていたんじゃないかと思いました。皆さんはどのあたりの生き物までがコミュニケーションをとれる限界だと思いますか。
山川 僕は歌を歌うので、肺呼吸をするかどうかがボーダーかな(笑)。鳥の場合は、肺呼吸をしている時点でコミュニケーションできる感じがする。でも秋田公立美術大学には唐澤太輔先生という粘菌の専門家の先生がいらして、唐澤先生は粘菌とコミュニケーションされていると思うので、お話を聞いてみたいですね。そうすると肺魚みたいな魚もいるから、肺魚ともコミュニケーションできるんだろうかとか、いろいろ考えてしまいますけどね。
山口 人間は動物と一言で言ってしまいますけど、その中にはいろんな動物がいて、共感できる動物もいればできない動物もいると感じます。例えばシカって人間に大きさが近いので、山で歩いていると気付くとシカの足跡の上を歩いているんです。つまりシカとは通じ合える部分が大きいなと思うんですけど、シマリスってすごく近くまで来て、逃げなかったりするんですよね。なぜこの行動をしているのかがよく分からないという感じもあったりして。
でも大きさだけが基準なわけでもなくて、さっき鳥の話がありましたが、鳥は鳴き交わせるんですよね。意地悪な音を立てるとざわざわするとか、小さいけれどコミュニケーションができる気がするし、それは人にもよるのだと思います。ずっとその動物のことを考えるとその動物の視点が見えてくることもあると思うんです。また人間が持っている音声でのコミュニケーションが可能とか、視覚優位とか、体が似ているとか、そこからいろんなことが考えられて面白いなと思いました。
石倉 種よりは個体なんじゃないかなって気がします。僕は長いことウサギを飼っていて、すごいツンデレで僕が可愛がろうとすると逃げるんだけど、フルートやギターを弾くと耳を立てて聞いてくれるんですよ。

触らせてくれないのに音にはすごく反応してくれるその距離感に身もだえする感じ。これがすごく好きで。イヌ、ネコの触る感じよりも音を通じてつながっているでも触れない、その辺の身もだえ感を叶えてくれるのはウサギだけでしたね。あとカメも好きでした。
山川 動物とセッションができた時ってすごくうれしいんですよ。でも相手が自分と同じ感覚で共鳴しているわけでは絶対ない。相手は「音楽」とは思ってないと思うんです。そのずれが実は超大事で、そのずれが逆に人間とは何なのかを考えるきっかけになる気がするんですよね。
例えば縄文土器に残された縄文人の指の跡の凹凸に触れて、あぁここに指をぐってやったんだと感動して、何だか彼らのことを分かった気になってしまうんだけど、でも縄文人が見ていた世界と、僕らが見ている世界とは絶対違う。他者と共鳴した喜びにはすごく素直でいながら、安易には同じって思わないこと。自分の想像の及ばない領域を全力で想像して、絶対分からないんだけど、でも自分がわかっていない領域が存在することを知ることも重要だとあらためて思います。
石倉 僕が共異体という言葉で言いたいのはそういうことかもしれないです。人間化することでも、人間が完全に相手になることでもなくて、違うまま一時的に自分の心がつながる他者になり得る。僕らの体の中には何兆もの他者がいて、意識はしてないかもしれないけど、共存していて、でも完全に一体化していない。それがまだ僕たちは言語化し切れてないところだけど、音楽では当たり前なのかもしれないし、アートではみんなやっていることなのかもしれないと考えています。
◀︎前編:事例紹介
Profile

山口 未花子(やまぐち みかこ)
京都生まれ。北海道大学文学研究院准教授。専門は人類学。2005年よりカナダ・ユーコン準州において先住民の古老から狩猟採集を学ぶほか、内陸トリンギットの動物描写、西表島のイノシシ猟などについても研究している。現在は北海道で自分でも狩猟を実践したり、獲れた動物の毛や皮を使った工芸品の製作なども手掛けている。
著書に『ヘラジカの贈り物』春風社、共著に『生きる智慧はフィールドで学んだ』ナカニシヤ出版、などがある。
Profile

山川 冬樹(やまかわ ふゆき)
美術家、ホーメイ歌手、秋田公立美術大学准教授
自らの声・身体を媒体に視覚、聴覚、皮膚感覚に訴えかける表現で、音楽/現代美術/舞台芸術の境界を超えて活動。己の身体をテクノロジーによって音や光に拡張するパフォーマンスや、南シベリアの伝統歌唱「ホーメイ」を得意とし、これまでに16カ国で公演を行う。現代美術の分野では、マスメディアと個人をめぐる記憶を扱ったインスタレーション『The Voice-over』(1997〜2008/東京都現代美術館蔵)、「パ」という音節の所有権を、一人のアートコレクターに100万円で販売することで成立するパフォーマンス『「パ」日誌メント』(2011~現在)などを発表。
ハンセン病療養所(瀬戸内国際芸術祭/大島青松園)や帰還困難区域(Don’t Follow The Wind展/グランギニョル未来のメンバーとして)での長期的な取り組みもある。
Profile
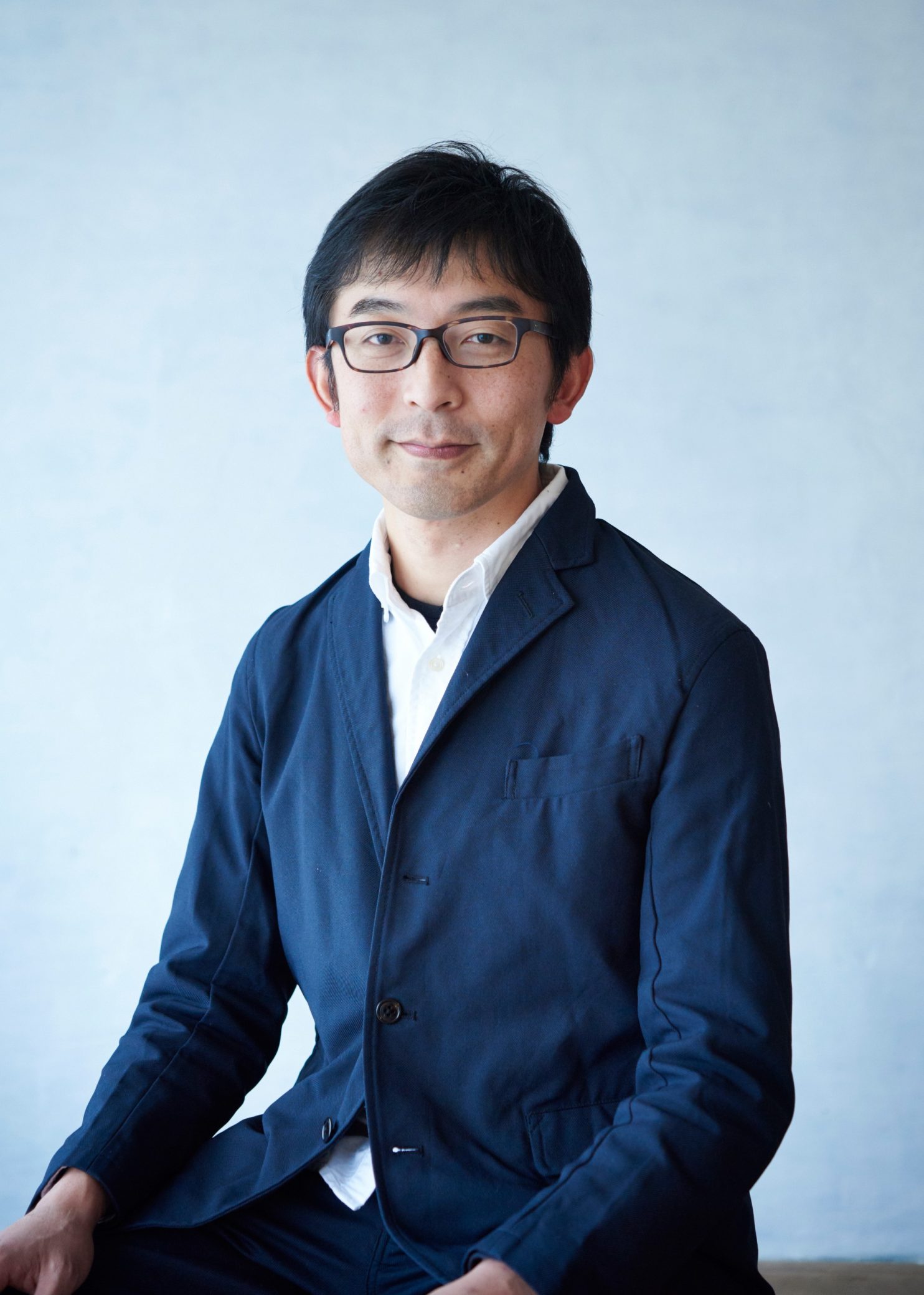
石倉敏明(いしくら としあき)
芸術人類学者、神話学者、秋田公立美術大学准教授
1974年東京生まれ。1997年より、 ダージリン、シッキム、カトマンドゥ、東北日本各地で聖者や女神信仰、「山の神」神話調査をおこなう。環太平洋圏の比較神話学に基づき、論考や書籍を発表する。近年は秋田を拠点に、北東北の文化的ルーツに根ざした芸術表現の可能性を研究する。著書に『Lexicon 現代人類学』(奥野克巳との共著・以文社)、『野生めぐり 列島神話の源流に触れる12の旅』(田附勝との共著・淡交社)、『人と動物の人類学』(共著・春風社)、『タイ・レイ・タイ・リオ紬記』(高木正勝CD附属神話集・エピファニーワークス)など。



撮影|伊藤靖史(Creative Peg Works)
構成|藤本悠里子(秋田市文化創造館)



