「未来の生活を考えるスクール」第13回開催レポート 前編
アニマルズ、ヒューマンズ、アスレチック
日時:2023年8月19日(日)14:00〜17:00
ゲスト:山口未花子さん、山川冬樹さん、石倉敏明さん
主催:秋田市文化創造館

新しい知識・視点に出会い、今よりちょっと先の生活を考えるレクチャーシリーズ、「未来の生活を考えるスクール」。
第13回では、狩猟の研究を行う人類学者の山口未花子さん、美術家・ホーメイ歌手として活動する山川冬樹さん、文化人類学と芸術表現の可能性を研究する石倉敏明さんをゲストに迎え、トーク・ワークショップを行いました。
秋田市文化創造館にて新たに始まったプロジェクト『〜になるためのトライアル』の一例となるユニークな活動を行うゲストを招き、「人間以外の種と交わりながら生きる術」そして「身体を使って表現をする術」について考えます。人間のために整えられた社会の中で薄まってしまった人間の能力、あり得たかもしれない人間のかたちを見つめ、これからあなたに訪れる「~になる」を自由に発想してみましょう。
山口さんトーク
私は文化人類学者として、カナダのユーコン準州の文化について研究をしています。面積は日本の1.3倍ですが人口は3万6000人ぐらいで、人間が非常に少ない場所です。そして大体が森や山や湖に覆われています。

2万6000年ぐらい前にアジアから人々が渡ってきて、現在は三つの先住民グループがいます。そのうちのほとんどを占めるのがファーストネーションズと呼ばれる人たちです。
私はファーストネーションズの中のカスカと内陸トリンギットというグループの調査をしています。お隣同士で暮らしている別々の集団ですね。環境や暮らしぶりは、よく似ていますが、文化を見ると違っています。それが如実に表れているのが音楽です。また、その音楽で何を表現しているのか、誰に対して歌っているのかというところも違っていることが分かってきました。
カスカと呼ばれる人たちは、狩猟採集文化を持ち続けて第1次世界大戦の後から定住化するんですけれども、定住前に生まれ育った人たちは狩猟採集に必要な知恵と技術を身につけていて、今も活発に狩猟採集を行っています。
この人たちと動物の間には、「クマと結婚した娘」や「カラスになったカスカ」などいろんな物語があります。日本でもツルがお嫁さんに来て、機を織って帰っていったという話がありますが、決定的に違うのはそれが本当に日常的に起こると認識していることです。集落と森の間に住んでいる甥っ子の家に毎日ヘラジカが来るようになったとき、私が一緒に暮らしていたおばあちゃんは、メスのヘラジカが甥っ子を結婚相手として狙っていると言いました。森の近くで人間と交わらずに暮らしていると、動物に結婚相手として狙われて連れて行かれてしまうという感覚を今でも持っています。
動物には、実際に狩猟したりするリアルな動物もいるんですが、動物の守護霊という存在もいます。動物の守護霊を持っている人たちは、生まれつきではなく、成長する段階で守護霊を手に入れます。手に入れ方はいろんな種類があるんですが、動物の霊、スピリットと交信するための手段として、非常に重要なツールの一つが音楽です。特にドラムをたたきながら歌を歌うということです。
ドラムをたたきながら動物と仲良くなっていくと、動物と波長が合うそうです。ラジオのチューニングを合わせるみたいにチャンネルを回していくと、動物の声がクリアに聞こえてくる地点がある。ドラミングがそれを助けてくれる。一度チューニングが合うといつでも合わせられるようになるという、非常に具体的な技術としてドラムを使った動物とのコミュニケーションがあると言っていました。
また狩猟においては肉を手に入れるだけではなく、動物が贈り物としてその体を人間にくれているという感覚を持っています。動物との贈与を通したやりとりが狩猟なので、ただ動物を殺してその肉を食べるということではなくていくつか儀礼をやります。
例えば気管を食べないで木の枝に吊るします。動物を銃で撃って倒れたら私たちは死んでいると言いますけれど、カスカの人たちはこれを死んでいるとは言わないです。なぜなら肺に空気を送る気管に魂が集約されていて、木の枝に掛けられて風が通るとまた息を吹き返して、肉を付けて皮を付けて元のヘラジカの形に戻る、つまり再生すると考えられているためです。

あるいは、ヘラジカの目玉を調理する前に必ず取り出します。全てのヘラジカは、他のヘラジカの目を通して、その目玉に映った世界を共有できるんですね。なので目玉が付いたまま焼かれたり煮られたりするとヘラジカに対して失礼になるので、調理する前に必ずくりぬいて森の中に置いておきます。そういうふうに動物からいろいろな物を得るために、動物にも配慮しながら暮らしている。常に動物に配慮する、語り掛けるというような暮らしをしてきた人たちです。
それに対して内陸トリンギットは、海のほうからやってきた人たちが内陸にいた人たちと混血してできた非常に新しい200年ぐらいの歴史を持つグループです。そういう二つの民族のルーツを合わせた人たちであることと、旅をしながら自分たちの民族性を維持してきた人たちなので、踊りと歌の中には動物だけではなくて人間が結構出てきます。
例えばお祭りのときや踊り、歌をするときに身にまとう物は、他の人に作ってもらった物しか自分の物にできません。自分が作った物を自分で着るっていうのはタブーです。ここには誰か贈ってくれた人がいるという人間関係が表れています。
ただ描かれているものは動物が最も多いです。トリンギットの人たちはトーテミズム的な社会制度を持っているので、生まれたときからオオカミクランの人、カラスクランの人、カエルクランの人というふうに決まっていて、それらしく振る舞うことが求められています。描かれるものは所属するクランを表す動物の紋章が基本的です。またトリンギットの人たちが作ったトーテムポールでは、祖先がどうやって旅してきて、この場所にたどり着いたかという歴史を伝えたりもしています。一番初めのほうでは、祖先が動物と結婚したり関わっていたりすることもあるのである動物との連続性だったり、海のほうから内陸にやってきた様子などが描かれています。
このトーテムをシンボルにして集団が集まるということが重要なので、1年に1回必ずいろんな地域にいるトリンギットの人たちが集まって、ダンスとか歌をパフォーマンスします。そのときに描かれた動物を身に着けつつ、でも人の絆みたいなものが顕在化する。だからトリンギットの人たちの実践を見ていると、動物だけではなくて人間という要素がカスカの人たちよりも強く表れているというような気がします。
このように、狩猟採集をしている人たちの動物との関わり方は一緒に見えても、その集団の歴史や人間関係の重要性、動物との付き合い方は違っていて、それが歌や踊りにはよく表れているなと感じています。
山川さんトーク

(鳥の囀りを声帯模写しながら登場)こんにちは。山川と申します。今、山口さんの方から「動物との連続性」というワードが出てきましたが、僕は子供の頃から動物のまねをするのが好きだったんですね。
今は音楽活動や美術活動をやりつつ、秋田公立美術大学で教員をやってるんですけれども、そんな僕に「動物への連続性」の感覚を教えてくれたのはまず音楽でした。『~になる』というこの企画。「~になる」芸術があるとすると、真っ先に思い浮かぶのは演劇だと思うんですよ。僕も役者をやらせていただくことも時々ありますが、演劇で「~になる」ということと、この企画でいう、「人間以外の物になってみる」こととは、究極的には同じかもしれないけど、でも、「演じること」と「~になる」というのは、やはりだいぶ違うことのように思える。僕の場合は動物になりきって遊ぶことが音楽の演奏につながってきたところがあって、今日はそんなお話から始めつつ、ずっとフィールドワークをしてきたハンセン病療養所で気づいたことなどをお話をできたらなと思います。
今、山口さんのほうから、カナダの先住民のお話がありましたけれども、僕がもともと歌を学んだのは、ロシア連邦のトゥバ共和国というところです。モンゴルの北西に接するロシア連邦に属する小さな共和国なんですね。ここに生きてきた人たちは遊牧民で、僕はそのトゥバの人たちから「ホーメイ」という歌唱法を学びました。モンゴルにはホーメイと非常に近い歌唱法のホーミーという歌唱法があって、トゥバとモンゴルは文化的には非常に近いんですけど、言語は全然違っていてトゥバ語はむしろトルコ語に近かったりします。
そこで学んだホーメイという歌をちょっとだけやってみます。

トゥバ共和国は恐らく地球上で一番海から遠い所なのですが、トゥバの人たちはそこで遊牧しながら、こんな感じの歌を歌い継いできました。トゥバのホーメイの特徴は、自然の描写が音楽になっていることです。例えば、今使ったイギルという擦弦楽器で風の音を描写したり、人間が声で動物の声をまねたり、あるいは動物が走っている様子を声で模倣したり。そうやって人間が自分の喉や楽器で自然を模倣していくことによって、自然から力をもらえるという考え方が根底にあるそうです。それがいわゆる声の芸術、音楽になっているんですね。
トゥバ共和国に行くと、とにかく広大な自然があり、もちろん風景は美しいんですけど、何もかも違って、例えば時間の流れも全然違う。僕が行った一番暑いときは気温が52度まで上がり、冬はマイナス30度台まで下がります。首都のクズルから車で少し行った場所でも草原が延々と広がっていて、もしここに一人で取り残されたら死ぬなっていう命の危険を実感させられます。すごく生き生きしてく感覚と同時に、人間すぐ死ぬな、みたいな感覚が常に隣り合わせにある、ホーメイとは、そんな中で生まれてきた歌なんですね。
ホーメイは僕のいろいろな表現のベースになっています。もともとはロックやクラブミュージック、いろいろな音楽が好きでやってきたのですが、ロックでがんがんノっているとき、クラブでがんがん踊っているときって、どこか自分の野生が目覚めてくるみたいな感覚があると思うんですよ、皆さんの中にもね。僕はティーンエージャーの頃からずっと音楽で身体を動かして熱くなる、楽しむことをやってきた中でホーメイに出会って、より自分の身体を駆使しながらいろんな表現に応用していくという活動をしてきました。
こうした音楽活動の一方で、近年はハンセン病療養所でフィールドワークを続けています。ハンセン病療養所はハンセン病患者の方たちが強制的に隔離されてきた場所です。療養所とは名ばかりで、事実上の強制収容所だったんですね。今ではもうハンセン病患者はおらず、全員とっくに治っているんですけれど、いまだにいろんな差別や問題が残っていて、療養所からふるさとに帰れず、日本全国の13の療養所に入所していらっしゃるという状況です。
僕がよく通っているのは大島青松園という瀬戸内海に浮かぶ離島・大島にある療養所です。ここには三十数名の方がいらっしゃって、ここに通いながらリサーチをしたり入所者の方と関わりながら作品を作り、島の中で発表したりしています。そもそもは瀬戸内国際芸術祭がきっかけで、この島に通い、いろいろアートプロジェクトに従事するようになったんですね。
ハンセン病の隔離政策は、日本の近代化そのものです。ハンセン病の隔離政策は明治初期に始まり、日本が先進国として欧米の列強と肩を並べようとするときに、ハンセン病患者の存在を「国辱」と考える思想があって、強制隔離によって社会から排除したという歴史があります。つまり近代化の過程で、日本が表向き華やかに見えるためには、ハンセン病患者たちは存在してはいけなかった。日本においてハンセン病隔離政策は、近代社会の基本原理になっている生権力による隔離や監視、あるいは統計という手法による国民の管理といった政策が国策として徹底的に行われた事例と言えるでしょう。
このすごく重い歴史を持った島で、僕はアーティストとして瀬戸内国際芸術祭に参加することになり、リサーチを始めたんですけれども、最初はこの島で自分に何ができるんだろうとすごく悩んだんです。その時に『ハンセン病文学全集』という本に出会い、その中で政石蒙さんという方がいらっしゃることを知りました。お名前の「蒙」はモンゴルの「蒙」ですね。かつて日本ではトゥバのことを外蒙古と呼んでいた頃もあり、この「蒙」という字に惹かれて政石蒙さんの『花までの距離』という随筆、短歌を収めた本を読んでいったんです。そこで自分が歌を学んだ風景がこの随筆の中に書かれている、とすごく衝撃を受けました。
政石蒙さんは15歳ぐらいにハンセン病を発症するんですが、進行が遅い病気なので発症し始めた最初の頃は外見ではまだあまり分からないんです。本人は皮膚の違和感から気づいていましたが、自分がハンセン病であるということは隠しながら生きていました。

当時はハンセン病ということが周りに知られると、人間扱いしてもらえない時代だったわけです。政石さんは自分がハンセン病だと悟って自殺も考えるんですが、戦争で自分がハンセン病だと知られないうちに死ねば、英霊として死ねる、それで死ぬために戦争に行きました。しかし一回も戦闘に遭わないうちに日本は敗戦、政石さんはソ連軍の捕虜となり、モンゴルで抑留されました。そして抑留される過程で身体検査があってハンセン病であることが発覚してしまい、捕虜収容所の中の隔離小屋にたった一人で隔離されるんですね。
そこで、政石さんが最初に詠んだ歌が、『足元の土をならして書きつける孤独の文字をよぎる蟻一つ』という歌です。隔離小屋の外にはちょっとだけ出ることができた。でも外には線が引かれていて、線の外へ出ると遠くから見張っている兵士に撃たれてしまう。その線の手前の土をならして「孤独」という文字を書くと、その上を蟻が横切っていったという歌です。
僕はこの作品に出会って、政石さんの生きた軌跡をたどるようにして、政石さんのふるさとに行ってご親戚の方に会ったり、政石さんが隔離されていたモンゴルまで行ったり、旅をしながら作品を作りました。
政石さんの作品には、動物たちへのまなざしにすごく特別なものがあります。虫や鳥や花々、あるいはオオカミたちやラクダたちとか、隔離される中で出会った人間以外の命に向けられたまなざしが、作品にとても豊かに現れています。例えば代表作『花までの距離』では、隔離の境界線が引かれたちょっと先に、きれいな花が咲いていて、自分に語りかけてくる。そして、その花がどうしても欲しくなるんです。でも線から向こうに行くと撃たれてしまうので絶対出られないわけですよ。その花を何とか自分の所に引き寄せようと、この線をもうちょっと広げていいですかと看守や医師に交渉したりして、最終的に花が自分の手元に来る。しかし、自分の手元に花が来たら、その花は色あせ、自分に語りかけなくなってしまったという終わり方をするんです。自由を求めて少しずつ理想的な方向に行きつつ、それが少しだけ実現してもまたすぐ色あせてしまう、そういったリアルなジレンマを描いた作品だと思います。
また隔離小屋から風景を眺めていると、遠くのほうにヤクやウシやウマがいるわけです。
私の心は私の肉体を離れて曠野へさまよい出た。かげろうのようにゆらめきながら私の心は、野にちらばって遊んでいる家畜たちの間を縫いながら、どこまでもさまよっていく。私は放心してガラス玉のようになった眼で心の行方を眺めた。私の肉体も心を追っかけていきたくてうずうずしているのに、重い鎖が私を結えていて身動きができない。私はうずくまったまま、心が肉体へ還ってくるまで待つよりないのだった。(政石蒙『花までの距離』より抜粋)
これは、身体は不自由な状態で隔離されているけれども、自分の心は身体から抜け出て草原をさまよい、ウシやウマと戯れていくイマジネーションの世界を書いているんだと思うんです。
政石さんはこの後、何とか復員して日本に帰るも、ハンセン病を患っていることが周囲に知れると、家族全員村八分にされてしまうような状況なので、ふるさとにいられないわけです。それで大島青松園に入られました。ハンセン病療養所では必ずみんな宗教団体に入信したんです。それは心の救済という意味や家族や、社会から切り離されるので、何かコミュニティーに属するという意味もあったと思います。でも政石さんはどの宗教にも入らなかった。これは療養所ではすごく珍しいことで、相当強い意志で宗教に属することを拒否していたと考えられます。その代わり政石さんは花や昆虫や獣と自らを重ね合わせる、彼らの世界の中に入っていくことができるアニミズム的な感性を持った人でした。そうやって動物や植物の世界に想像的に入っていくことによって、人間の残酷な社会から一時的に自由になる術を知っていた。ただ重要なのはそうやって一時的に人間の社会から自由になることで自らを救う術を知っていながら、そこにまた引き戻されてしまう現実もよく理解していて、アニミストであると同時にリアリストでもあったと思います。
政石さんのことを考えていて、今日ふと思い出したのが、テレンス・マリックが監督した『シン・レッド・ライン』という映画です。これはガダルカナルの戦いを描いた映画なんですけど、この映画で印象的なのが唐突に挿入される森や動物たちのショットなんですね。人間の視点を超えたカメラアイがアニミスティックな視点と重ね合わされ、殺し合う人間たちがまるで動物たちや森に見られているかのようで、その視点の反転が強い反戦のメッセージになっている。
またもう一つ思い出したのが、『セプテンバー11』という2002年に公開された9.11をモチーフに様々な映画監督が短編を撮ったプロジェクト中の、今村昌平監督『おとなしい日本人』という作品です。これは、戦争で負傷して帰ってきた勇吉という兵士がただヘビになってしまうという非常にシュールな映画で、家族のことを家族として認識せず、腹ばいでひたすらにょろにょろ這って終わる。戦争という非人間性の極みの果てに、アニミズムとアナーキズムが合流してくような、すごい作品だと思います。
芸術って人間にとってどういう意味があるだろうって思った時に、例えば僕は時々オオカミのようにほえてみたりするのですが、動物になってみた瞬間に野生化していく感覚があるんです。そうはいってもそのままオオカミになったら生活できないので、我に返って戻ってくるんだけど、一時的にたがを外してみることによって生きていける、みたいな感覚があります。そういった野生を取り戻す方法論として芸術が機能するというのは多々ある。特に音楽は、すごくそれがある気がします。
一方で芸術はすごく理性的な営みでもあって、かつてハンセン病というだけで人間扱いされなかった時代のなかで、政石さんをはじめとするハンセン病療養所に生きた人たち活動には、芸術という非常に理性的な営みを実践することによって、自分が人間であることを証明していくという意味もあったと思います。
人間が人間以外の種と交じり合い関わり合いながら生きていく、表現するといったときに、戦争やハンセン病の隔離など、近代が生み出した非人間的な極限状態の中で、一時的にアニミズム的なものを求める人間の性のようなものを、紹介した事例の中に見つけることができるんじゃないかと思います。
石倉さんトーク
今、山口さんと山川さんのプレゼンを聞いて、動物って現実的であると同時に想像的でもあるという、その二つの側面が人間にとって重要な他者だということが共有できたと思います。僕からもまさに想像ということを通して、動物をどう捉えてきたのかというお話をこの東北に結び付けて話したいと思います。

僕は人類学をやっている一方で神話の研究もしています。神話はまさに人間が想像した世界の物語ですね。神話を持ってない社会はないといわれるくらい実は神話は普遍的なものです。歴史の物語と神話の物語、二つの側面があって人間が人間になれるのかなと僕は思っています。
最初に見ていただきたいのが、うちの子どもが2年前に新聞で作った動物で《新聞タイガー》と《魚》です。トラは街の中に普通に歩いている動物ではないので、動物園の中や新聞や映画などのメディアを通して見るものだと思うんですけど、子どもたちは現実の動物と同じくらい想像の動物と触れ合って交じり合っている。うちの子どもは釣りが好きで、魚を釣るときには魚と現実的に交じり合っているんですけれども、一方で魚の形がどうだったのかを思い出して新聞で作り、動物の中に人間と共通するものを見いだしたり決定的に違うポイントを探ったりしている。これは造形やアートの深い部分につながっているのかなと思います。
去年の11月にはキメラ動物といういろんな動物が混ざったようなイメージを描いてきたんです。いろんな動物を混ぜて描いていくということは、人間の表現の中でもとても根源的なものだと思います。
そのルーツを探ってみると、紀元前400年にエトルリアで作られた『アレッツォのキメラ』という有名な彫刻があります。ライオンとヘビとヤギなど、既に存在する動物たちが混ざっているイメージです。あるいはスフィンクス、これもいろんな動物が混ざり合って人間の神話の中に登場するものです。特にイタリアにはハイブリッドなキメラが神話の中に住んでいて、キリスト教世界の中にも忍び込んでいます。エトルリアからローマにかけては、墓地にライオン像を作るという習慣がありました。つまり人間の生と死を守る物として、想像的な動物種が描かれているわけです。
動物を想い描くということは、個と集団を結ぶ想像力と結びついている。そして自分が生きる世界をどういうふうに現実化していくのかということに関係していると思いました。人間は人間だけで生きていないので、人間の周りに住んでいる他者としての動物を想い描き、それを具体的に造形し描くことによって、想像と現実を串刺しにすることをやっているのだと思います。
今までのキメラの研究では、共同体がどういう幻想を抱いたのかにポイントを置かれてきましたが、僕はむしろ人間が人間ではない物たちと作っている共異体、つまり異なる物同士が異なったまま共存するという社会の在り方の中で、どう現実を描いているのかということに関心があります。共同体の幻想よりも共異体の現実として、架空の存在がどういうふうに共有されてきたのかということです。
架空の怪物のような存在を描かない社会は珍しい。もちろんなかなか出てこない社会もあるんですけれども、ただ文明が発展すればするほど、他者のイメージも逸脱を許容するようになってくるという側面もあるように思います。実際に現代アートの中にも、こういうイメージがあふれてくるわけですね。

ゴードン・ホワイトという人は、イヌとオオカミの神話が共同体のへりに関わるということを言っています。例えばイヌの頭をした守護聖人がキリスト教の神話に出てくるんですけど、それはキリスト教世界の内側にあるんです。これに対してオオカミの顔をした人狼は共同体の外にある。オオカミとイヌという近い種を通して、人間の外と内という他者の関係を表す一つの記号になっていることが見えてきます。
日本ではオオカミはイヌと連続していました。ヨーロッパは牧畜社会なので、オオカミが敵だったんですけど、日本では神だったんですね。江戸時代まではオイヌサマといって、オオカミが害獣をよけてくれるとむしろ積極的に信仰されていた文化がありました。そしてもう一つ、貴族階級の中でトラによって権力を象徴していた絵画が、トラのいない庶民の絵の中ではオオカミに置き換わっていくという特徴があったようです。異国から伝来したトラという見たことがないけど強いというイメージが、身の回りにいる強い存在であるオオカミに置き換えられていく。そういう記号として貨幣のように置き換えられていくことがあったわけです。実際、僕がフィールドワークした中でもいまだにオオカミの骨を持って、害獣よけをしているっていう文化が東京の武蔵御嶽神社の周辺や埼玉の三峯神社の周辺にありました。
現代アートの中にも人間と動物のハイブリッドのイメージが生きています。人間が動物と交わる仕方には、現実に他者として交わるという他にもイメージの中で混ざっていく、あるいは変身していくというもう一つのベクトルがあるように思います。そう考えると、人間の中にある動物性、動物の中にある人間性、そのあわいにあるキメラというものに大きな魅力が潜んでいるのではないかと思えるわけです。
2010年に東京都現代美術館で行われた『東京アートミーティング トランスフォーメーション』という展覧会の中で、アーティスト・人類学者のイルコモンズさんたちと一緒に「変容人類学研究室」という展示を担当しました。これは人間が変身するということを考える上で、どんなバリエーションがあり得るのかというアーカイブです。このときには「他のかたちへなっていく=Becoming Others」「ヒトのかたちに変わっていく=Becoming Human」「超人化していく=Transcending Human」「逸脱していく=Transcending Nature」という四つの軸を設けて、この中で変容の内在と超越のモデル化を考えてみました。その中には動物だけではなくて、サイボーグやウルトラマン、仮面ライダー、妖怪、怪獣、さまざまな人間ならざるものへの変身というテーマが、含まれていきます。そうすると動物は最も近い他者であると同時に、人間と動物の間にはさまざまな人工的、あるいは自然的な変容や逸脱というものが含まれていると想像することができます。
最後にシシ踊りの説明をしますが、シシというのは大型の四つ足の動物全般を指します。ニホンカモシカやイノシシ、カノシシ、ニホンシカなどですね。そして人間が動物になるのがシシ踊りや獅子舞だったりするんです。

ライオンみたいな日本にはいない動物とすぐ隣に住んでいるような動物が同じシシという概念で扱われていた。
例えば東北の古い狩猟法では布をまとった猟師が、ニホンカモシカのまねをするんだそうです。そうすると、カモシカはじっと布を見入ってしまって動かなくなる。そのときに鉄砲でズドンと撃つような猟があったといわれています。
岩手県北上市の釜津田鹿踊りでは、お盆の時期にお墓の前で動物に変身して、お線香とお経を上げていくんですけど、なぜ人間がわざわざ動物に変身して死者にお参りするのか。これは東北の不思議な文化ですが、他者というのは動物であると同時に、死者でもあるということです。シシ踊りは日本海側では獅子舞が多くて太平洋側ではシシ踊りが多いのですが、特に北東北ではこの二つの境界があいまいで混ざり合っている。人間以上のもののイメージを喚起して、それと一体になるという踊りになっています。
シシ踊りは二つの系統があって、おなかの前で太鼓を叩くのが太鼓踊り系というもので、幕を持ってお墓の前で踊るのが幕踊り系です。幕踊りは死者儀礼として死者の前でお参りや供養をするものです。特に重要なのは万霊供養といって、有縁のご家族や親族のお参りをするだけでなく、行き場のない無縁仏や動物の霊、人間ではない物たちも一緒に、無差別にお参りする存在になっていることです。
これは今の人類学者が言っている「人間ではないものたちとの関係を表す、あるいは人間以上の関係を表す」ということと関係しています。エドゥアルド・コーンという人類学者は、ルナ族というアマゾンの民族がインコよけのかかしを作って、畑に金剛インコが寄りつかなくすることを、人間から金剛インコに向けた記号と言っています。人間ではないものに向けたアートとも言えます。
沖縄石垣島白保の獅子舞では獅子が赤ちゃんを口から飲み込んで、おなかから出すということをやります。子どもが2度目の誕生を迎えるように飲み込んで、おなかから出すことで真人間になる、大人になっていく第一歩を刻むという意味を持っています。
非常に面白いのは、岩手県早池峰の権現舞でも幕で人間を囲って、同じように生まれ直しをするんです。獅子の体内に入ることで獅子に食べられて、もう一度体内から生まれ直すという踊りが、石垣島と岩手というとても離れた地域に残っています。
このように獅子舞や獅子踊りには、実在する動物から想像する動物までのさまざまなイメージが複合しています。そして、生まれて食べて食べられて死んでいくというある意味では人間が動物と共通している部分、また決定的に違う部分を表しているのではないかなと考えています。
▶︎後編:鼎談、質疑応答
Profile

山口 未花子(やまぐち みかこ)
京都生まれ。北海道大学文学研究院准教授。専門は人類学。2005年よりカナダ・ユーコン準州において先住民の古老から狩猟採集を学ぶほか、内陸トリンギットの動物描写、西表島のイノシシ猟などについても研究している。現在は北海道で自分でも狩猟を実践したり、獲れた動物の毛や皮を使った工芸品の製作なども手掛けている。
著書に『ヘラジカの贈り物』春風社、共著に『生きる智慧はフィールドで学んだ』ナカニシヤ出版、などがある。
Profile

山川 冬樹(やまかわ ふゆき)
美術家、ホーメイ歌手、秋田公立美術大学准教授
自らの声・身体を媒体に視覚、聴覚、皮膚感覚に訴えかける表現で、音楽/現代美術/舞台芸術の境界を超えて活動。己の身体をテクノロジーによって音や光に拡張するパフォーマンスや、南シベリアの伝統歌唱「ホーメイ」を得意とし、これまでに16カ国で公演を行う。現代美術の分野では、マスメディアと個人をめぐる記憶を扱ったインスタレーション『The Voice-over』(1997〜2008/東京都現代美術館蔵)、「パ」という音節の所有権を、一人のアートコレクターに100万円で販売することで成立するパフォーマンス『「パ」日誌メント』(2011~現在)などを発表。
ハンセン病療養所(瀬戸内国際芸術祭/大島青松園)や帰還困難区域(Don’t Follow The Wind展/グランギニョル未来のメンバーとして)での長期的な取り組みもある。
Profile
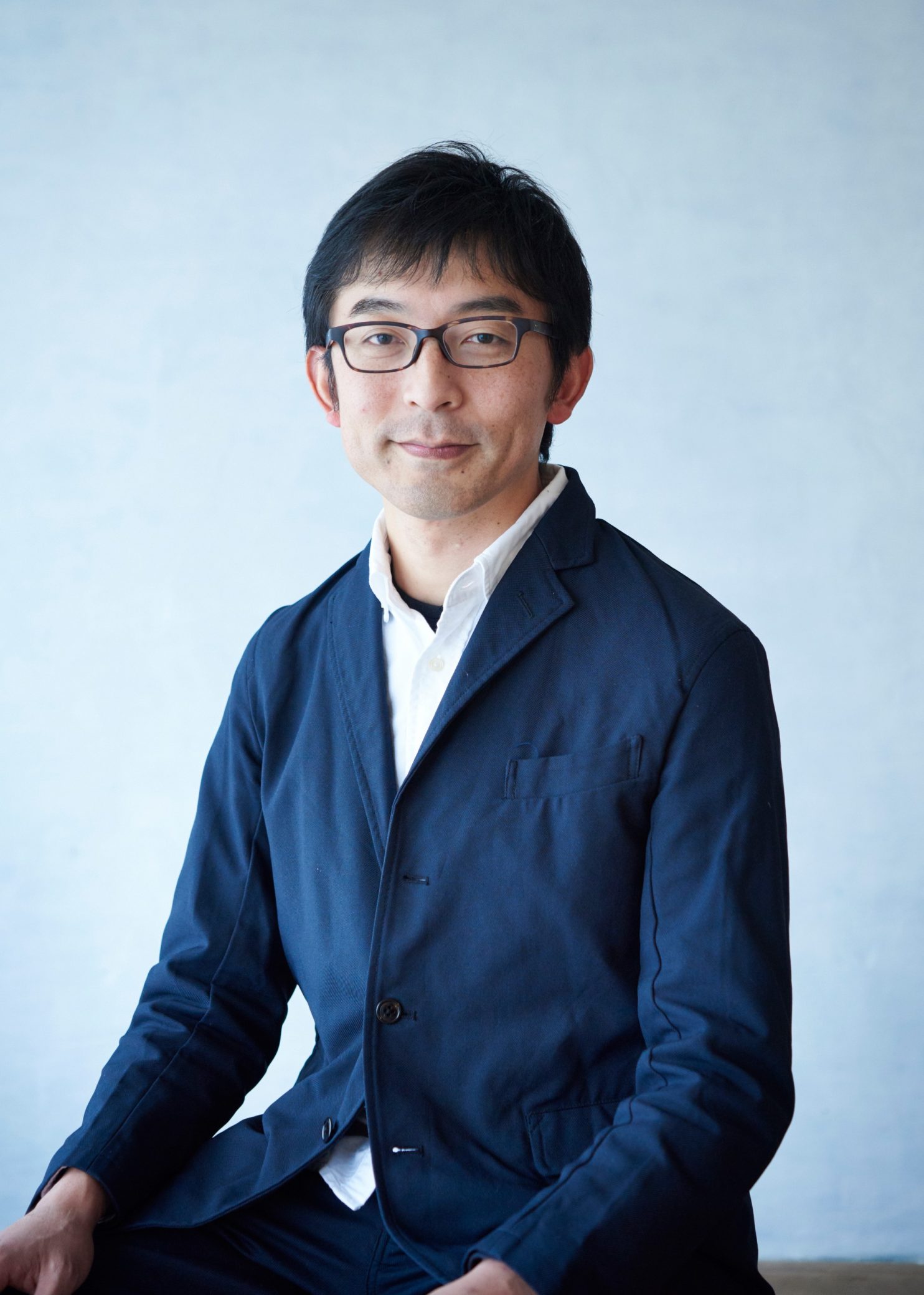
石倉敏明(いしくら としあき)
芸術人類学者、神話学者、秋田公立美術大学准教授
1974年東京生まれ。1997年より、 ダージリン、シッキム、カトマンドゥ、東北日本各地で聖者や女神信仰、「山の神」神話調査をおこなう。環太平洋圏の比較神話学に基づき、論考や書籍を発表する。近年は秋田を拠点に、北東北の文化的ルーツに根ざした芸術表現の可能性を研究する。著書に『Lexicon 現代人類学』(奥野克巳との共著・以文社)、『野生めぐり 列島神話の源流に触れる12の旅』(田附勝との共著・淡交社)、『人と動物の人類学』(共著・春風社)、『タイ・レイ・タイ・リオ紬記』(高木正勝CD附属神話集・エピファニーワークス)など。





撮影|伊藤靖史(Creative Peg Works)
構成|藤本悠里子(秋田市文化創造館)



