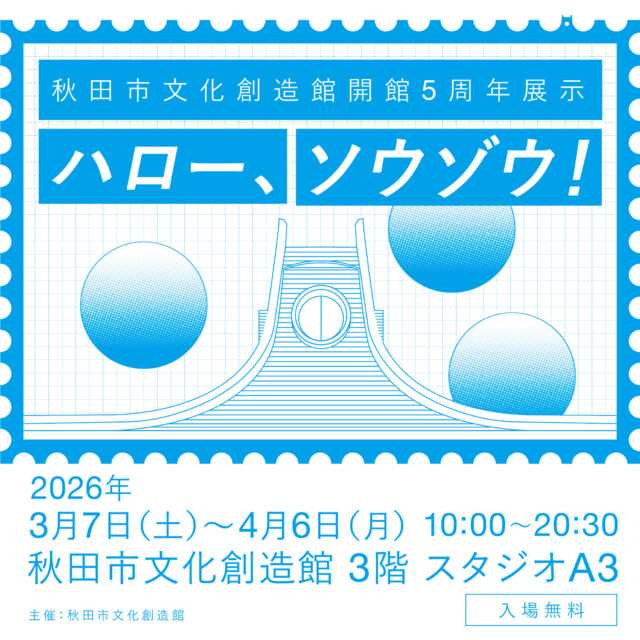クロストーク
「やまはげ、なまはげはどこから来るのか?」
〜下浜桂根のやまはげ、上新城のなまはげをめぐって〜
2025.11.1

●下浜桂根のやまはげ:藤原浩一、川村均
●上新城のなまはげ :髙橋浩樹、佐田稔
●特別講師:齊藤壽胤
●聞き手:渡辺知(秋田市農山村地域活性化センターさとぴあ)
かつて秋田市下浜桂根地区で行われていた、どこかユーモラスなお面の「やまはげ」。
上新城で100年近く続く、小又集落と白山集落が協力しあい今も執り行う「なまはげ」。
二地域の代表者が共通の課題を語ります。
基調講演と解説は、秋田の伝統行事、民俗学の研究者である齊藤壽胤氏にお願いします。
開催概要
日時:2025年11月1日(土)13:00〜15:00
会場:秋田市文化創造館 2階 スタジオA1
定員:50名(無料・要申込み)
共催:秋田市農山村地域活性化センターさとぴあ+秋田市文化創造館
予約・問合せ:018-893-6424(秋田市文化創造館)
●来訪神
地域に長く息づいてきた伝統的な文化があります。人と人、人と地域が結びつく行事として大きな意味を持っています。その文化が、高齢化や人口減少、若者の流出などで廃れ消滅する事態が各地で起こっています。
この度、「下浜桂根のやまはげ」「上新城小又・白山のなまはげ」二つの行事を継承してきた関係者が、共通の課題を語りあうクロストークを企画しました。
問題意識を共有しながら取り組むべき「地域づくり」についてあらためて考える場をつくります。基調講演は地域の伝統行事、民俗学の研究者である齊藤壽胤氏にお願いします。
●下浜桂根のやまはげとは
10年ほど前まで秋田市下浜桂根地区で行われていた小正月行事です。起源については、明治期にはすでに行われていたとされています。下浜地区全体で「やまはげ」行事が行われてきましたが、2025年現在は、長浜、羽川、八田、楢田地区のみとなっています。
下浜桂根のやまはげは、お面をつけた若者が各家を訪れ、無病息災や五穀豊穣を祈願し、子どもたちを見守る大切な行事でした。男鹿のナマハゲに似ていますが、藁で作られた大きな鼻とぎょろりと大きな目玉が特徴です。昨年、秋田市農山村地域活性化センターさとぴあではお面づくりのワークショップが開催されました。
桂根地区のみ、毎年「面」を制作する点や、担い手が若年である点など、独自のならわしが発展・継承されてきました。面に刺す御幣も町内の方々による手製です。
昭和36年ころから10年ほどの中断期間を経て、「桂根親の会」により復活したものの、子どもの数の減少やライフスタイルの変化の波を受けて、平成25年ころに再び中止となりました。
お面▶ざる、かご、桟俵、トタンなどをベースに、12月になると子どもたちが主体となって毎年制作。どこかユーモラスで、作り手のセンス頼り。「かぶる」というより「持つ」もので重量感がある。手づくりの御幣を頭部に刺す。使い回さず、行事が終わるとすぐに焼却するため、過去のものはほぼ残っていない。
装束▶腰蓑、ケデ、面を3点セットで装着。
●上新城小又・白山のなまはげとは
100年近く続いているといわれている行事ですが、小又集落と白山集落の住民有志で作る「双葉親交会」が行事を継承し、現在は1月15日に小正月行事として行われています。当日のケラの製作も担います。
地域の地主のもとで働く「わかぜ=若勢」や「めらし=女性の使用人」に、お餅を食べたり、お酒を飲んだりしてほしいという、寺の和尚(日徳山昌東院:臨済宗妙心寺派)の思いから始まったといわれています。
昨今、高齢化によりケラ編みができる人が減少し、世代交代がスムーズに進んでいないところもあるようですが、それでも、双葉親交会の皆さんは、小正月の日に楽しみに待っている住民のためにも存続に尽力しています。
男鹿の風習をベースにしているのではないかと推察されますが、神社信仰との結びつきはみられず、各家々に配るお札も行事主体である双葉親交会が作成し、昌東院で祈祷を受けたものを使用しています。
以前は、小又・白山以外でも執り行われていたが、現在はこの2地区のみ。全世帯が訪問対象で、子ども向けの行事というわけではありません。親交会の現メンバーが途絶えると、行事も途絶えてしまうことが危ぶまれています。
お面▶購入した木彫面を使用。双葉親交会所有のものが2点(男鹿の面彫師に依頼したもの)、個人所有のものが2点。
装束▶ケラをまとう。行事直前の日曜日に、新年会を兼ね双葉親交会で作成(1時間ほどで完成)。家々を訪問し終わると、その日のうちにどんと焼きで焼却。
Profile
齊藤壽胤 (さいとうじゅいん)
昭和29年、秋田市雄和生まれ。國學院大学文学部神道学科卒業。 神道学、民俗学を専攻して平田篤胤佐藤信淵研究所専任研究員、日本海域文化研究所主任研究員などを経る。現在、鶴ヶ崎神社宮司、NPO法人日本民俗経済学会理事、秋田県民俗学会副会長、秋田県民俗芸能協会会長。平成9年NHK東北ふるさと賞、平成17年日本民俗経済学会研究賞、平成27年神道文化会学術表彰、平成30年度秋田市文化選奨、令和5年度秋田市文化賞などを受賞。テレビ、ラジオのレギュラー出演多数。
著書に『男鹿五里合の民俗』(監修・著、秋田文化出版)、『秋田の民俗つれづれに』(傳承拾遺の會)、『感性の国学者平田篤胤』(彌高叢書第12輯)など。共著に『日本伝説体系・北奥羽編』(みずうみ書房)、『在地伝承の世界・東日本編』(おうふう)、『秋田市事典』(国書刊行会)、『年中行事大辞典』(吉川弘文館)など。
ポスターデザイン:佐藤豊
問合せ
〒010-0875 秋田県秋田市千秋明徳町3-16
秋田市文化創造館
電話|018-893-6424 (9:00-21:00/火曜日休館 ※休日の場合は翌日)
メール|program@akitacc.jp (熊谷/勝谷)