2024年度 秋田市文化創造館 外部評価委員 テキスト
新しい活動や価値を生み出していくことを基本理念に据える文化創造館では、「管理の効率化」や「市民の平等な利用」を主軸とする既存の指定管理の評価指標のみでは測りきれない成果がうまれていると実感しています。県内外の文化芸術、まちづくり、教育等の多様な分野の専門家を招き、文化創造館の成果や課題について議論を蓄積する場として、2022年度より外部評価委員を設置し、委員の方々から多様な評価コメントをいただきました。
委員メンバー(五十音順、敬称略)
上松 留美(ハラッパAFTER SCHOOL 代表)
大澤 寅雄(NPO法人アートNPOリンク 理事長)
小倉 拓也(秋田大学教育文化学部 准教授)
工藤 尚悟(国際教養大学 准教授)
林 千晶(株式会社Q0 代表取締役社長)
三浦 崇暢(秋田市仲小路振興会 副会長)
上松 留美
文化創造館は私が運営する学童からは距離にして徒歩2分ほど。開設当時から変わらず手入れが行き届いた庭で、鬼ごっこや水遊び、館内ではワークショップに参加させていただきました。子どもたちに興味関心をもってもらいたいと思う展示にはみんなで足を運び、五感を使った刺激をたくさん受けることができました。アーティストさんとの距離が近く、直接やり取りをしながら肌で感じることができ、創造館は好奇心が育つ場所だと思っています。
昨年夏には蓮のお堀に遊歩道ができ、これまで以上に外国人を含むたくさんの人々が行き交う様子が見られました。利用者が多種多様になってくるとその対応も様々で、解決が難しい案件を持ち込む人がいたり、専門性に関係なく細かなことに応えていかなければいけなかったりなどいろいろです(これは近隣で商売をしている私の店舗でも同じです)。
また、利用者が増えにぎやかになることは嬉しいことですが、より安全性に気を遣う必要性も出てきます。普段の仕事の他に、見えない家事ならぬ見えない仕事が増えることは免れません。丁寧に対応することを大切しながらもスタッフの負担を減らす、利用者の満足度を上げる、という課題をどう解決していくのか、創造館の長所を活かした運営を改めて考えなくてはいけないときなのかと思います。ただの貸館事業ではなく、ここにくれば何かワクワクするものに出会える場所、心地よい刺激の中から生まれてくることを一緒に広げていける場所になってほしい。完成されたイベントや、少し難しく感じてしまう講演などだけではなく、ふらっと立ち寄って、遊びやクリエイティブな発想の空間を楽しめる場所(場所だけではなく人的環境も)があると、もっと子どもたちにもやさしい場所になるのではないかと思っています。
文化創造館の専門性とは何か? 創造館だけですべてを抱え込まず「芸術文化ゾーン」としての認知度を上げ、美術館や芸術劇場ミルハス、にぎわい交流館AUなどのそれぞれの専門性を活かすエリアとして、様々な「もの」や「こと」を共有し、柔軟にこの場所を創り上げてほしいと思っています。
Profile

上松 留美 Rumi Uematsu
秋田市千秋矢留町の学童保育施設「ハラッパAFTER SCHOOL」代表。またヨーロッパ製玩具のセレクトショップ「PLAY+TOYS のはらむら」を運営するほか、こどもの探究心や好奇心・創造力の芽を伸ばすイベント「あそびのはじまり」をプロデュース。秋田県社会福祉審議会児童福祉専門分科会委員。秋田市中小企業振興推進会議委員。秋田市行政改革市民委員会委員。
大澤寅雄
文化創造館に限らずほとんどの公立文化施設の場合、設置者である自治体が施設の運営や事業を評価する際に、施設の利用件数や来館者数といった数値指標が評価の対象となる。施設の維持管理や事業運営にかかる支出=コストに対して、どのような成果・効果=パフォーマンスが生まれているかというコスト・パフォーマンス、いわゆる「コスパ」が自治体の関心となる。市民に対する説明、事業や施策の見直しの大きな要素となっている。
文化創造館も例外ではなく、重要な指標の一つではある。しかし、利用件数や来館者数をパフォーマンス、指定管理料をコストとして割り算をした結果は、その公共施設の価値を適切に評価しているのだろうか。少なくとも文化創造館は「コスパの向上」だけでは、この施設の価値を高めることにはならない。コストが一定のままで、パフォーマンスを無理に向上させようとする考え方にはリスクがあると私は考えている。
今年度、私は数名の職員に対してヒアリングを行う機会が与えられ、これまでの文化創造館の成果や課題をどのように捉えているかを各職員に質問をした。職員は各自の専門性を発揮しながら担当業務にやり甲斐を感じており、運営管理や事業企画で利用者に喜んでもらっている手応えを感じていた。一方で、利用の増加に伴い業務分担の見直しと変更があり、職員間のコミュニケーションに不足を感じていると見受けられた。また、2024年度は離職する職員が相次いだ。各自のライフステージの変化やキャリア形成の意向と考えるが、職員各自の専門性を踏まえ、能力や成果に見合った雇用条件となっているか、検討が求められる。
現状の指定管理者制度の運用では期間が限定されており、一定の指定管理料で雇用される職員数や報酬の水準には限度がある。その中で利用件数・利用人数を右肩上がりに増加させることは、職員の疲弊を招き、心理的・時間的な余裕や余白を奪い、利用者へのサービスの低下やリスク対策の不足などの問題が発生しかねない。こうした課題もまた文化創造館に限らず、公益社団法⼈全国公⽴⽂化施設協会が2023年に発表した「劇場、⾳楽堂等における指定管理者制度運⽤への提⾔」[1]で「官製ワーキングプアを生み出す弊害」について触れているように、ほとんどの公立文化施設が抱えている大きな課題、しかも喫緊の課題である。
アプローチは二つ考えられる。ひとつは、成果や効果、つまりパフォーマンスの捉え方を利用件数や来館者数といった外形的・表層的な数値だけで測定するのではなく、内面的・深層的な変化を観察し、運営管理計画に沿って丁寧に言語化し、指標化や数値化を試みることだ。もうひとつのアプローチは、指定管理料、つまり設置者である秋田市のコストの見直しである。予算の現状維持では職員の負担軽減やパフォーマンスを持続させることが困難ではないか。
外部評価委員として、これまでの文化創造館の成果や地域への波及効果を高く評価するとともに、今後も維持し発展させていくために、とくに人件費に充当する予算の増額を求めたい。これは、わが国の多くの公立文化施設が抱える共通課題でもあり、秋田市と秋田市文化創造館が、その課題に立ち向かう先鞭となることを期待する。
[1] 劇場、⾳楽堂等における指定管理者制度運⽤への提⾔(公益社団法⼈全国公⽴⽂化施設協会、2023年10月)https://www.zenkoubun.jp/info/2023/1024.html
Profile
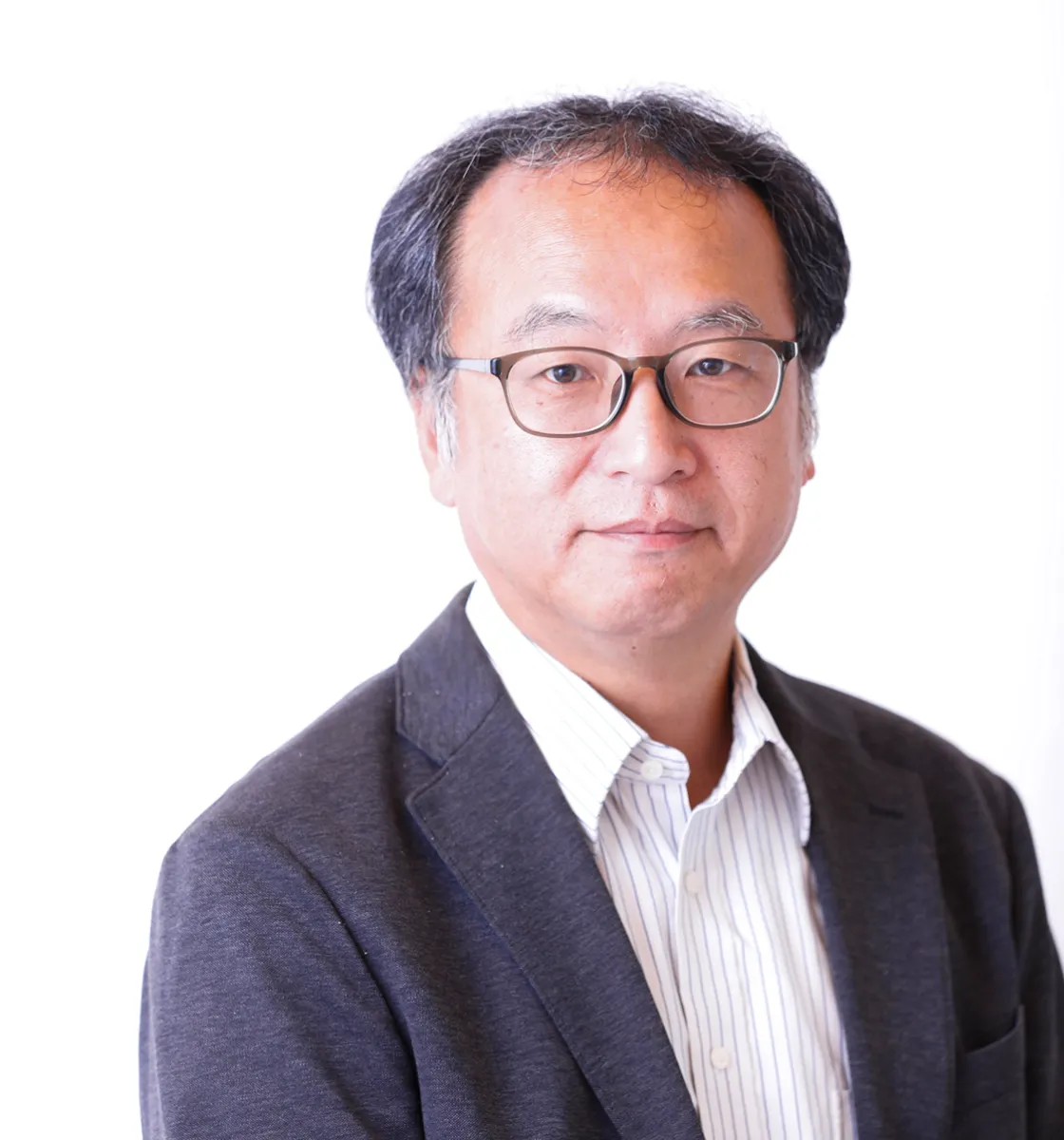
大澤寅雄 Torao Osawa
1970年、滋賀県生まれ。1994年、慶應義塾大学卒業後、株式会社シアターワークショップにて公共ホール·劇場の管理運営計画や開館準備業務に携わる。2003年、文化庁新進芸術家海外留学制度により、アメリカ·シアトル近郊で劇場運営の研修を行う。帰国後、NPO法人STスポット横浜の理事および事務局長、玉川大学および跡見学園女子大学の非常勤講師(文化政策論、アートマネジメント等)、東京大学文化資源学公開講座「市民社会再生」運営委員、株式会社ニッセイ基礎研究所芸術文化プロジェクト室主任研究員を経て2023年6月に文化コモンズ研究所代表·主任研究員に就任。
小倉 拓也
秋田市「文化創造プロジェクト」の拠点として、市民を主体とした文化的、創造的な活動を担ってきた文化創造館は、順調な利用者数増という量的な点でも、利用者からの高い評価という質的な点でも、そのミッションを着実に実現している。公共施設でありながら前衛的なアートプロジェクトも行い、多様な市民を巻き込む場となる施設としては、全国的に見ても例外的と言っていいほどの成功を収めていると言えるだろう。今年度は、商業誌の移住先特集 (1) や、法人機関誌の文化交流施設特集 (2) でも紹介され、名実ともに秋田市の「顔」となりつつある。
特筆すべき取組みとしては、国内外、県内外からのアーティストの滞在制作の受け入れ先となるクリエーター・イン・レジデンスの実施と展開をあげることができる。文化創造館ではこれまで、国内のアーティストをゲストに迎えて実施してきたが、その経験を踏まえ、海外アーティストも念頭に、プログラムを質的にも規模的にもさらに展開していく準備を整えることができた。2025年度のプログラムはすでに公募中であり、過程も含めその活動に期待している。
今後必要となるのは、このような高い評価に値する活動を、持続可能な、健全なかたちで維持、促進していくことである。順調な利用者数増は、現行のスタッフの数とフィジカルなキャパシティからすると、超過気味になりつつあるとも言える。利用者目線で見ても、休日の施設予約はかなり早い段階で埋まっている傾向にある。もちろん、これはスタッフの努力ゆえのことであり、スタッフのスキルの高さ、仕事への取組みの真摯さを示すものである。スタッフの増員や施設の老朽化への対処などに必要な予算を確保し、投じることが、秋田市にとって急務だと言える。
上記のとおり、文化創造館の活動はいまや秋田市の「顔」にもなりつつもあり、持続可能で健全なかたちで維持、促進していくことが求められる。ここで避けて通れないのは、人件費、つまりスタッフの給与等の待遇面の改善である。現在、官民ともに賃上げが行われているが、それでも物価高騰等により実質賃金は下がり続けている。文化創造館のような指定管理者による高度に専門的な仕事に対しても、適切な対価が支払われなければならない。人口減少に直面する秋田市が、必要な対価を支払わないことでみずから人口流出に拍車をかけるなどということはあってはならない。外部評価委員として、秋田市には、給与、待遇面の改善のための予算等の措置を強く求めたい。
(1) 『田舎暮らしの本』2025年2月号、宝島社、2025年、59頁。
(2) 『地域創造』第50号、一般社団法人地域創造、2024年、9-15頁。
Profile
プロフィール写真-1.jpg)
小倉拓也 Takuya Ogura
秋田大学教育文化学部准教授。博士(人間科学)。専門は哲学・思想史。美学や精神医学などの研究も踏まえて「形」や「リズム」の哲学に取り組んでいる。著書に『カオスに抗する闘い――ドゥルーズ・精神分析・現象学』(人文書院)など。
工藤 尚悟
- 生活の動線のなかに文化創造館を
文化創造館を拠点に、自分たちの思いや考えを定期的にイベントにして実現する人たちが増えてきた。こうしたいつもの利用者の外側に、文化創造館はどのようにリーチできるだろうか。「文化を創造する」という行為を、秋田に暮らす人々の生活の動線のなかに位置づけていく。そんな新しい目標設定のタイミングにきているのではないか。自分のなかにやってみたいことが具体的にある人たちの表現の場としてだけではなく、今の自分がどんなことを考え感じているのかに気が付くために、文化創造館に行ってみようという感覚を生み出せないか。難しいが、とてもエキサイティングな挑戦である。
- 小さな企てに取り組み、大きなイベントに圧倒される
文化創造館に集まる人たちが企画するイベントやプロジェクトが、まるで泉のようにたくさん生まれてきている。秋田に暮らす人々が生み出す小さな企てのホットスポットであり続けると共に、アートエキシビションやシンポジウムなどの大きなイベントに触れられる場でもあって欲しい。展示や対話の中身に強く共感したり、はっとさせられたり、スケール感に圧倒されるような経験ができる場としての役割にも期待したい。
- 多世代が混ざる場所として
文化創造館が秋田にある意味とはどのようなものか。ひとつには、秋田の風土のなかで紡がれてきた自然観や民俗を継承しながら、その先にどのような新しい文化を生み出していくのか、ということがあるだろう。この意味を具現化するには、多世代が混ざる場所が必要だ。文化創造館で行われている様々な活動において、既に世代の異なる人々が対話し、協力しあう場面が多くある。人口減少が続いていくなかでも、文化の継承と創造において、賢く手を動かしていく秋田であって欲しい。こうした領域での文化創造館の役割は極めて大きい。
Profile

工藤尚悟 Shogo Kudo
国際教養大学国際教養学部グローバル・スタディズ領域・准教授。東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了(博士・サステイナビリティ学)。南アフリカ・プレトリア大学アジア研究センターリサーチアソシエイト。専門は、サステイナビリティ学、まちづくり、地域研究。秋田と南アフリカの農村地域を行き来しながら、異なる風土にある主体の邂逅から生まれる“通域的な学び(Translocal Learning)”というコミュニティ開発の方法論の構築に取り組んでいる。秋田県能代市出身。近著に『私たちのサステイナビリティ:まもり、つくり、次世代につなげる』岩波書店。
林 千晶
最近は秋田に行く際にできるだけ来館している。イベントが催されていると1階は多くの利用者や来館者でいっぱいだが、イベントがないときは閑散としている様子。利用件数が伸びているというが、空いているスペースはあるので、今後まだまだ来館者数が伸びるバッファはあるだろう。
ただ、誰にでも貸して、貸しテナント業のような働き方や場所になるのはもったいない。文化創造館は「みんなに開かれた」場所を目指している。「みんな」とは誰か?それは「メインストリーム」に対する「オルタナティブ」な「みんな」であったと理解している。「公共空間」の「オルタナティブ」なあり方を示す事例を見せているのではないか。ちなみに「みんな」なんてものは無いと思っている。あえて、こういう人に使ってほしい、逆に「他人の音が気になる」など、こういう人は使用を控えてもらったほうが賢明と言っても良いから、「みんな」という言葉は無くしてもいいのではないだろうか。
開館して1、2年目は正直よくわからない施設だったが、そのことが余白を感じさせてすごく良かったと思っている。そして多様な実績ができてきた4-5年目に入ってきた今、改めて文化創造館が何のためにあるのか、こんな利用者が多いなどを発信するフェーズに入ってきている。「つくる」イメージを強化することを文化創造館が決めたのならば、「つくる」といっても、どういう「つくる」行為があって欲しいかをもっと発信するべき。どんなふうに使われているのか、何が生まれているのかはまだ十分に発信されていない。
例えば、ソウゾウカンラボやリソグラフについて使い方の成功事例、モデルケースを見せてもよい。その時に「こういう風に使ってください」と言うのではなく、「こんな風に使えるよ」、「使い方はあなた次第」というスタンスも合わせて伝えるのが文化創造館の姿勢なのでは。
つまり、利用件数よりも利用事例や成功事例を増やすことこそ大事。
そして、つくったものをここなら売ることもできる。ここは美術館じゃない。文化創造においては、流通を生む仕掛けも必要。ただ単にきれいだね、と見て終わらない。究極的にはアートやデザイン、クリエイティブな「仕事」を生み出す機会につながっているはず。「創業支援」と言うと違う印象があるが、最終的にはそこに向かうのでは。一人ずつが生きていくために、アートやデザインについての起業家を醸成しているのは、実は文化創造館。そんな風に考えている。
Profile

林 千晶 Chiaki Hayashi
株式会社Q0 代表取締役社長。花王を経て、2000年に株式会社ロフトワークを起業、2022年まで代表取締役・会長を務める。退任後、株式会社Q0を設立。秋田・富山などの地域を拠点において、時代を代表するような「継承される地域」のデザインの創造を目指す。グッドデザイン賞審査委員、経済産業省「産業競争力とデザインを考える研究会」などを歴任。森林再生とものづくりを通じて地域産業創出を目指す「株式会社飛騨の森でクマは踊る」取締役会長も務める。
三浦 崇暢
秋田市文化創造館(以下「創造館」とする。)について、外部評価委員会指摘事項への取組状況と創造館が今後課題としている事項を基に評価していく。
まず、外部評価委員会指摘事項の取組状況を確認していく。新規の方への周知活動、他都市や類似事業者からの注目度や他施設との連携については、新規企画への取組みや既存事業をブラッシュアップするなど、前向きな姿勢が感じられる。一方、昨年同様労働環境の取組状況、そして労働形態にも関わってくる施設利用の在り方とその対応、さらには施設管理者としては避けては通れない施設の安全維持管理については、創造館としても課題に感じている部分が多くあるように思う。これらの点については、次段落から評価をしていく。
創造館において、労働環境と施設利用、施設の安全維持管理この3つは密接に絡みあっていると私は考えている。今年度、管理チームと事業チームが統合するという労働環境において大きな変化があった。これにより人材育成やチームワークの構築、属人性の深度を緩和分散させていくことができるだろう。しかし、仕事のモチベーションについての不満がでてくるのは必須である。事実、離職者も増えている。離職者が増えれば新しい人材を確保しなければならないが、昨今の就活事情を考えると、既存スタッフへの給料より高額な給料を提示しなければ入社してくれない可能性がある。仮に、新規人材が入社したとしても、そのスタッフの給料の高さに不満を感じた既存スタッフが離職するかもしれない。そして、金銭の問題でいうと施設の安全維持管理も十分な懸念が想定される。建物維持管理への委託費や修繕に伴う経費は物価高騰と賃金増加のあおりを受けて高くなる一方である。この流れは今後も続くだろう。事業計画の見直しや、不足財源の確保について協議し、建物修繕については計画を長期化させ毎年の支出を抑えつつ最低限の修繕を実施していくなどの工夫が必要だろう。
しかし、何の事業をするにも要になるのは人である。事業の長期継続化を考えた際、効率を求めると管理事業チームを統合するという選択肢を選ぶことは分かるが、仕事量の増加に伴って、既存業務や新事業の展開等に支障がでては意味がない。話は変わるが創造館への主な相談一覧を拝見した。相談内容は、創造館の利用についての相談以外に身近な話、個人的な話など多岐にわたっていた。正直、通常の貸館では考えられない相談内容であり、相談されても「分かりません」で一蹴されそうなものだが、創造館スタッフは親身な対応を心がけているようだった。確かに、お客様第一主義の観点から言うと痒いところに手が届く素晴らしい対応なのであろうが、良くも悪くも相談受け取りの幅の広さが周知されれば、今以上に本業に関係のない業務が増えてくるだろう。このようなことは自由度の高い創造館だからこそ起こりえる悩みなのであろうが、ある程度マニュアル化して白黒はっきりさせた方が、管理事業チーム統合の効果が表れると思う。
いろいろと書いてきたが、ここ数年で労働環境や建物管理を改善するために必要な資金の状況が大幅に変わってきた。重点分野とそうでない分野を明確にしたうえで、年間の収支予算と突き合せ、中長期計画を見える化させることが肝要だ。そのうえで、不足分を補うための事業を検討していきたい…と書きたいところだが、創造館はただの貸館ではなく地域の文化醸造、アートなまちづくりに一役買って出る場所である。先立つものがなければ事業もへったくれもないのは分かっているが、営利だけを求める場所ではなく秋田の様々な人がこの場所で何かを創っていく場所であることを考えると、行政からの補助金が今以上に必要なのでなないかとも思う。
Profile

三浦 崇暢 Takanobu Miura
仲小路振興会 副会長。秋田市生まれ育ち。大学卒業後は、大手製薬メーカーの営業として就職。2014年に秋田へ戻り、家業の有限会社三浦産業(不動産業)に入社し現在に至る。秋田市中心街のスキマ空間、公園、空き物件の活用を好き勝手に考えて実行するゆるい有志の集団「堀を語る会」で活動中。



